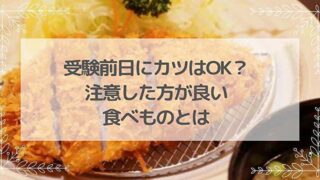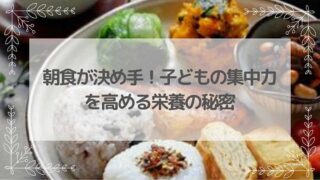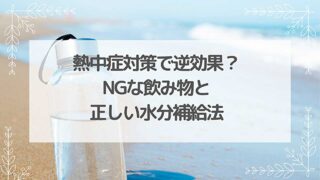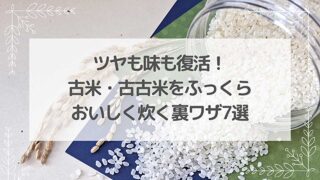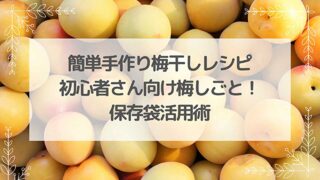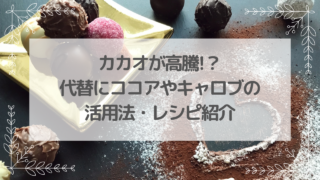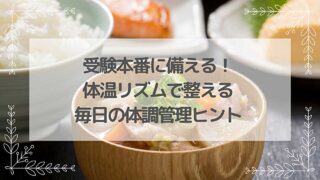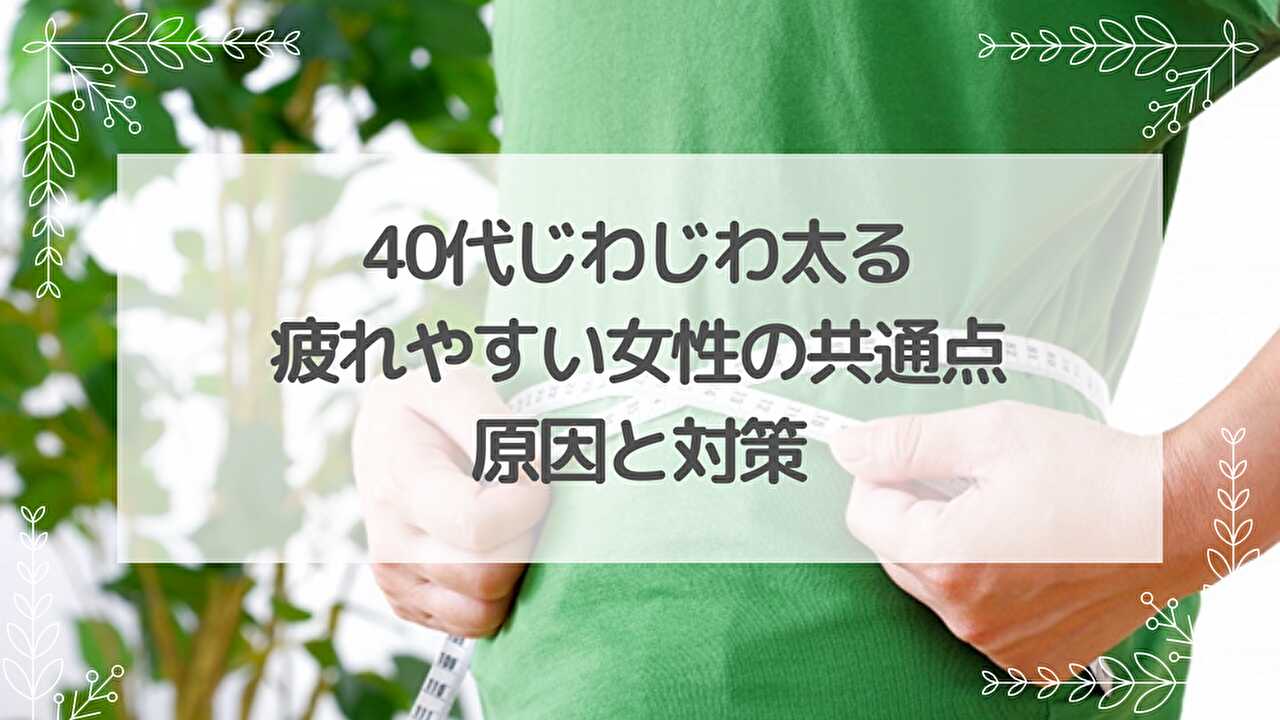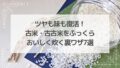こんにちは。
40代以降、多くのお母さんが「なんだか疲れやすくなった」「昔と同じ量を食べているのに太ってしまう」といった体の変化を感じるというお声をよく聞きます。

食べる内容も変わらないのに・・どうしてそうなるのでしょうか。

その背景には加齢に伴うホルモンバランスの変化や代謝の低下といった、誰もが通る「加齢に伴う自然な体の変化」が関係していますが、私も含め誰もが通る道です。
家族やお子さんの健康や学業を支えるには、まずお母さんが元気であることが大切です。
本記事では、お母さん自身の体調を整えることが、家族全体の健康と日々の安心につながるという視点から、代謝と食生活の関係についてやさしく解説します。
代謝が落ちるとどう変わる?体重・筋肉・疲れやすさへの影響は
一般的に 中年期は40歳〜64歳ごろを指し、ライフステージでは働き盛り・家庭の責任が大きい時期ですね。
女性の 閉経前後10年間(平均的には45〜55歳ごろ)で主に 女性ホルモン(エストロゲン)の急激な変化により、心身にさまざまな症状が出やすい時期です。
この40代以降の「中年期」には、代謝や筋肉量の変化が起こりやすく、体重や体調に影響します。

なかでも更年期に入ると、筋肉が徐々に減少することやホルモンの変動などいくつかの要因が重なり、脂肪をため込みやすく太りやすい体質になったり、更には疲れやすくなったりした経験する人も多いでしょう。
更年期のホルモンの変動が脂肪のつきやすさに
更年期は一般的に体の内側ではホルモンのバランスが少しずつ変化していきます。
この時期、女性ホルモン「エストロゲン」の分泌が急激に減少していきます。
✅エストロゲンには、次のような働きがあります
- 脂質代謝をサポート(中性脂肪やLDLコレステロールの増加を抑える)
- 血管の柔軟性を保ち、血流を促進
- インスリン感受性の維持(糖の代謝を助ける)
特に女性は、更年期に差しかかることでエストロゲン(女性ホルモン)が大きく減少し、脂質の代謝がうまくいかなくなったり、中性脂肪や悪玉コレステロール(LDL)が増えやすくなったりします。
結果的に、脂肪をエネルギーとして使いにくくなり、内臓脂肪が蓄積しやすくなります。

筋肉はエネルギーを消費する組織なので減ることで基礎代謝も下がり、太りやすい体質へと変化してしまうのです。
筋肉量が減ることでエネルギー消費も減少
年齢を重ねると、筋肉が少しずつ減っていく傾向があります。
これが「太りやすくなる」「疲れやすくなる」原因のひとつでもあります。
筋肉は、呼吸や体温調節など、生きていくうえで無意識に使われる基礎代謝の中心的な役割を担っています。
この基礎代謝量は、年齢や性別、筋肉の量によって異なり、特に年齢とともに自然に低下します。
筋肉が減ると、動いていないときでも消費されるエネルギーが減り、1日の消費エネルギーが少なくなるため、太りやすくなってしまうのです。
使いきれなかったエネルギーが体内に蓄積され、脂肪として残りやすくなるので、同じ食事量でも太りやすくなると感じるのです。
日常の動きが減り消費エネルギーもダウン
40代以降になると、仕事や家事、家族のサポートなどで時間が取られ、意識的に体を動かす機会が減ってくる人が多くなります。
若い頃に比べて活動量が落ちると、当然ながら1日のエネルギー消費も減少します。
そんな中で、食事量が以前と変わっていなければ、余ったカロリーが体脂肪として蓄積されてしまい、体重が増えていく…という流れになります。
自律神経の乱れも影響
ホルモンの変動は、自律神経にも影響を与えます。自律神経は、内臓の働きや代謝、体温調節などを司る重要な役割を持っています。
ホルモン分泌の指令を出す視床下部は、自律神経の司令塔でもあるため、更年期のホルモンの乱れは自律神経の乱れにも直結します。
結果として、
- 睡眠の質が低下し、食欲ホルモンのバランスが崩れる
- イライラや不安感から、甘い物や炭水化物に手が伸びやすくなる
- 疲れやすくなり、活動量が減る
といった悪循環が体重増加に拍車をかけることもあります。
次に身体につく脂肪について、みていきましょう。
内臓脂肪と皮下脂肪の違い|増えるとどうなる?
身体につく脂肪は大きく分けて、「内臓脂肪」と「皮下脂肪」の2つに分類されます。
この2つはつく場所や性質が異なるため、それぞれの特徴を知っておくことが、健康維持や体型管理の第一歩になります。
内臓脂肪とは?
内臓脂肪は胃や腸といった内臓のまわりにたまる脂肪で、必要以上に増えると生活習慣病のリスクを高める原因になります。
とくに40代以降になると、加齢やホルモンバランスの変化によって内臓脂肪がつきやすくなり、メタボリックシンドロームの一因になることも少なくありません。
ただし、内臓脂肪は食事の見直しや適度な運動で比較的減らしやすいという特徴もあります。意識して生活習慣を整えていくことで、改善が見込める脂肪のタイプです。

40代以降の体重増加は、特に閉経後の女性は、エストロゲンの低下による内臓脂肪の蓄積が関係しているケースが多いです。内臓脂肪は、見た目だけでなく生活習慣病のリスクを高めることも。そのため、体重よりも体脂肪の質(つき方)に目を向けることが大切です。
皮下脂肪とは?
一方、皮下脂肪は、皮膚のすぐ下にたまる脂肪で、お腹やお尻、太もも、腰まわりなど、特に女性に多く見られます。
体がエネルギーを蓄えておく“備え”としての役割もありますが、過剰にたまると体型の崩れや冷え、むくみなどの原因にもなりやすいです。
皮下脂肪は一度つくと落ちにくく、継続的な運動とバランスの良い食生活がカギになります。
食事でできる対策|更年期世代は“質とバランス”がカギ
中年期の体重増加をゆるやかに防ぐためには、まず食事の内容を見直すことが大切です。
特に、脂肪の蓄積に関わる内臓脂肪や皮下脂肪をコントロールするには、単にカロリーを減らすだけでなく、三大栄養素のバランスにも目を向けることが重要です。
「PFCバランス」とはタンパク質(Protein)・脂質(Fat)・炭水化物(Carbohydrate)という3つの栄養素を、1日の総摂取エネルギーの中でどのような比率でとるかを示す考え方です。
このバランスを意識することで、代謝がスムーズに働きやすくなり、健康的な体重の維持に役立ちます。
PFCバランスを意識|おすすめ食品
三大栄養素(Protein=タンパク質・Fat=脂質・Carbohydrate=炭水化物)のバランスを整えることで、効率的にエネルギーが使われやすくなります。それぞれの推奨される割合は以下のとおりです(合計で100%になります)
| 栄養素 | 目安(%) | 意識したいポイント |
|---|---|---|
| タンパク質(P) | 13〜20% | 筋肉量の維持 セロトニンの材料になる |
| 脂質(F) | 20〜30% | オメガ3脂肪酸など 良質な脂を意識 |
| 炭水化物(C) | 50〜65% | 精製糖質を控え 血糖値の急上昇を避ける |
無理なく代謝を高め、内臓脂肪や皮下脂肪を上手にコントロールするためには、日々の食事や過ごし方を少しずつ見直していくことが効果的です。
PFCバランスや五大栄養素については、こちらで詳しく解説されています。

ここでは、取り入れやすい具体例をいくつかご紹介します。ご自身のライフスタイルに合うものから、ぜひ参考にしてみてください。
タンパク質をしっかりと
筋肉を保つために欠かせないのが、タンパク質です。

筋肉量が維持されると、基礎代謝も落ちにくくなり、脂肪の燃焼効率も高まります。日々の食事で意識的に取り入れてみましょう。
- 朝食例:納豆・焼き鮭・卵焼きなど
- 昼食例:鶏むね肉のグリルや豆類を使ったサラダ
- 夕食例:サバやサーモンなどの魚料理、豆腐を使ったメニュー
脂質は「量」より「質」を意識
脂質はカットするものと思われがちですが、体に必要なエネルギー源でもあります。特に不飽和脂肪酸を含む食品は、脂肪燃焼や血流改善にも役立ちます。
- サラダや料理にはオリーブオイルやアボカドをプラス
- サバ・イワシ・マグロなど脂ののった魚を週に2〜3回取り入れる
- 間食に素焼きのナッツ類を選ぶ
炭水化物の「選び方」と「量・質」に気を配る
炭水化物を控えるのではなく「何を選ぶか」が大切です。血糖値の急上昇を避けられる炭水化物を意識することで、脂肪の蓄積を防ぐサポートになります。

「質の良い炭水化物」とは、血糖値の上昇がゆるやかで食物繊維やビタミン・ミネラルも一緒に含まれているような食品を指します。
- 白米⇒分搗き米や雑穀米をプラス
- うどん⇒蕎麦やオートミールなど
- 精製パン⇒全粒粉のパンに置き換えて
- おやつ⇒甘いお菓子の代わりに果物やナッツや干し芋など
- 食物繊維が豊富な野菜やきのこを、毎日の食事にたっぷりと
精製されたものではなく“精製されすぎていない自然に近い形”が、体にやさしく脂肪になりにくく質の良い炭水化物としておすすめです。
食べる時間にもひと工夫
「何を食べるか」に加えて「いつ食べるか」も体脂肪に関係します。
特に夜遅い食事は体に脂肪が蓄積されやすくなるため、タイミングを整えることが大切です。
- 夕食は寝る2時間以上前には済ませるのが理想
- 運動前には少量の炭水化物、運動後にはたんぱく質を摂ることで筋肉回復をサポート
水分も代謝に影響する
水分不足は代謝の低下につながることも。意識的に水分を補給することで、体内のめぐりをサポートし、脂肪の燃焼効率を高める効果が期待できます。
- こまめに水やカフェインを含まないお茶などを摂る(1日1.5~2リットルを目安に)
- 特に運動をする前後には水分補給を忘れずに
運動と生活習慣の工夫で代謝アップ
筋肉を維持する運動を
健康づくりの目安として厚生労働省では「1日8,000歩程度の歩行」を推奨しています(2023年6月時点)。
もちろん個人差はありますが、日常に無理なく取り入れられる運動習慣として取り入れてみましょう。私も夜散歩を夫婦でやっています。
- ウォーキング・スロージョギング:週3~5回、1回20分以上が目安
- スクワット・体幹トレーニング:筋肉量維持で代謝サポート
糖質を極端に制限して短期間で体重を落とそうとする方法は、筋肉まで減ってしまう可能性があり、代謝が下がってリバウンドにつながることもあります。

食事のバランスを整えながら、ウォーキングなどの軽い運動を取り入れて、2~3か月かけて1kgずつ減らすようなペースが体にやさしく無理なく長く続けやすい方法です。
しっかり眠って自律神経をも整える
- 就寝前はスマホやPCを控え、睡眠ホルモン(メラトニン)の分泌を促進
- 趣味・深呼吸・軽いストレッチなどで副交感神経を優位に
睡眠に関する記事は、こちらで詳しく解説されています。
体重管理は、心と身体を“ととのえる”ことの延長線上にあります。
まとめ|40代からの体型変化は未来の健康のサインかも
体重が増えやすくなるのは、ホルモンや代謝の働きが変わってきたということです。

40代以降の体の変化は「衰え」ではなく、人生の次のステージに向けた“準備期間”とも言えますね。毎日を支えるお母さんが元気でいること。それが、家族の健康とお子さんの未来につながります。
これまでの方法が通用しなくても、「ご自身の身体と対話しながら調整する」ことができると、乗り越えていけるようになります。
「私に合った食生活って?」「今の体調、どこを見直せばいいの?」そんなお悩みがある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
こちらもチェック
- Blossomの大切にしている想いについて、詳しくはこちらをご覧ください
- Blossomのコンセプト Blossomの具体的な取り組みはこちらから
- ワークス
最後まで、お読み頂きありがとうございました✨