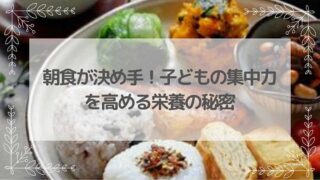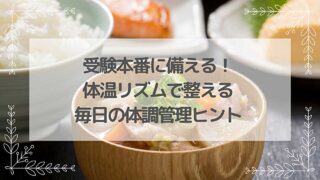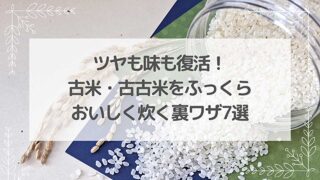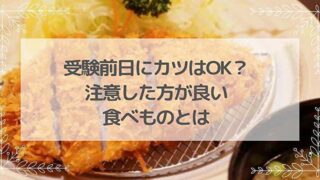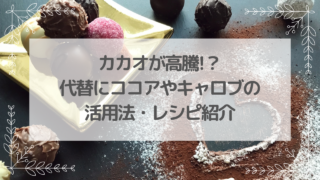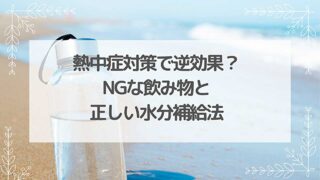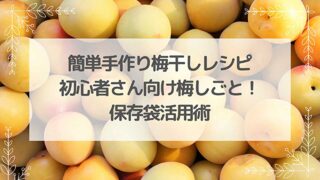暑い日が続いていますね。

最近“ペットボトル症候群”という言葉を聞きました。私も麦茶や炭酸水をペットボトルでよく飲むのですが、気をつけた方が良いのでしょうか?

同じペットボトルでも、ユウさんのように普段から甘くない飲み物を選んでいるなら大丈夫。ただ、暑い時期はつい冷たいジュースやスポーツドリンクに手が伸びがちですよね。知らないうちに糖分を取り過ぎると起きる症状のことなのです。
「なんだか最近、ずっとだるい…のども渇くし、食欲もない」
そんな不調、実は“水分補給の仕方”に原因があるかもしれません。特に夏場やスポーツ後に清涼飲料水を多く飲む方は要注意です。
今回は、近年注目される「ペットボトル症候群」について、症状や背景、日常生活でできる対策などを管理栄養士の視点からわかりやすく解説します。
ペットボトル症候群とは?
ペットボトル症候群とは、正式には「清涼飲料水ケトーシス」と呼ばれ、糖分を多く含む飲料(炭酸飲料、果汁飲料、スポーツドリンクなど)を短期間に大量摂取した結果、血糖値が急激に上昇し、代謝バランスが崩れる状態のことをいいます。
血糖値が急上昇すると、膵臓は大量のインスリンを分泌して血糖を処理しようとします。しかし、それでも追いつかないと、エネルギーがうまく使えず脂肪を分解します。
代謝異常により「ケトン体」が発生し「ケトアシドーシス」に陥ると、意識障害や脱水、昏睡といった症状に進行すると至ることもあるのです。

糖尿病の人以外でも、誰でも陥る可能性があるので注意が必要なのです。
次に、ペットボトル症候群になるとどのような症状が現れるのか、具体的にみていきましょう。
症状チェックリスト|もしかして当てはまる?
以下のような症状が続く場合は、飲み物の習慣を見直すサインかもしれません。
- 強いだるさや疲労感
- のどの渇きが続く
- 頻尿または尿の量が多い
- 食欲不振や吐き気
- 急激な体重減少
- ぼーっとする、集中できない
これらは高血糖や脱水のサインであり、糖尿病とも似ているため注意が必要です。違いを明確にするため、以下に比較表でまとめてみました。
| 特徴 | ペットボトル症候群 | 糖尿病 |
|---|---|---|
| 発症スピード | 数日〜数週間で急に 起こることがある | 長い時間をかけて 少しずつ進むことが多い |
| 主な原因 | 糖分飲料の過剰摂取 | 生活習慣や・加齢・体質などさまざまな要因 インスリン作用不足 |
| 年齢層 | 若年層にも多い | 中高年に多いが全年齢で発症可能性あり |
| 回復 対応の仕方 | 飲み物を見直し 必要に応じて医療のケアを 受ける | 医師の指導のもとで 日々の食事や生活を見直しながら うまくつき合っていくことが大切 |
このような症状が当てはまる場合は、日ごろの飲み物の選び方や生活習慣を振り返ることが大切です。
では、どんな人がペットボトル症候群になりやすいのでしょうか?次に、注意したい生活スタイルや傾向を見ていきましょう。
なりやすい人の特徴とは?|あなたもリスクがあるかも
症状が軽視されやすいため、以下のような方は特に注意が必要です。
- 夏場に食事を抜いて清涼飲料水ばかり飲んでいる
- 部活後に毎日スポーツドリンクを飲む習慣がある
- 成長期の子どもや受験生で、勉強中に甘い飲み物を飲むことが多い
- 小腹が空いたときに、甘い清涼飲料やゼリー飲料で済ませてしまう

清涼飲料水は、体に必要な水分補給とは別物です。「飲んでいるつもり」で、逆に体調を崩してしまうこともあります。
それでは、実際に私たちがよく手に取る飲料にはどれほどの糖分が含まれているのでしょうか?
清涼飲料水の糖分量|“甘さ”の見える化
私たちが日常的に飲んでいるペットボトル飲料には、どれくらいの糖類(主に砂糖)が含まれているか、実は知らずに飲んでいることがありませんか。
また「甘いけど、スポーツドリンクだし健康に良さそう」と思って手に取る飲み物も、水分補給というより“糖分補給”になっているケースが多いのです。
以下は、代表的な市販飲料に含まれる糖分の目安を角砂糖(1個=約3g)に換算したものです。
| 飲料名 | 内容量 | 糖分量(角砂糖換算) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 炭酸飲料(例:コーラ) | 500ml | 約14個分(42g) | 強い甘味・習慣化に注意 |
| スポーツドリンク | 500ml | 約8〜10個分(24〜30g) | 清涼感があり飲みやすいが高糖質 |
| 清涼果汁飲料(果汁30%未満) | 500ml | 約11個分(33g) | ジュース感覚でも糖は多い |
| エナジードリンク | 250ml | 約7個分(21g) | 容量は少ないが糖濃度が高い |
※製品により糖質量は前後します。表示成分をよく確認しましょう。
これらを「水分補給」として日常的に飲み続けると、気づかないうちに1日で50g以上の糖を摂取していることもあります。
特に、のどの渇きが強い夏場や、受験生・スポーツを頑張るお子さんにとっては、飲み物が“第二の食事”になってしまうことも。
だからこそ、「どんな成分がどれくらい含まれているのか」を知ることが、最初の一歩です。
飲み物選びのポイント|日常でできるリスク回避の工夫
では、私たちはどんな飲み物を選べばよいのでしょうか?ここでは、ペットボトル症候群のリスクを高めにくい飲み物の選び方や、日常生活での工夫について紹介します。
✅基本の水分補給は「水」や「麦茶(ノンカフェイン)」を選ぶ
無糖・ノンカフェインで、体にやさしく、日常的に摂っても負担が少ない飲み物です。特に麦茶は、ミネラルも含まれており、成長期の子どもや受験生にもおすすめです。
✅味の変化がほしいときは「レモン水」や「無糖炭酸水」「無糖ハーブティー」などを活用
香りや酸味で満足感を得られやすく、糖分なしでも「飲んだ気になれる」飲み方です。
✅スポーツ時や発汗量が多い場合は、電解質補給を目的にスポーツドリンクを“用途に応じて適量”取り入れる
スポーツドリンクは本来、脱水時のナトリウム補給が目的。日常的にがぶ飲みするのではなく、「熱中症対策用」「長時間の運動後」など必要なシーン限定で少量を選ぶことが大切です。無糖タイプの経口補水液やナトリウム入りミネラルウォーターの活用も選択肢です。
甘い飲み物は“嗜好品”ととらえ、1日1本までを目安に
→ 毎日のように何本も飲んでしまうと、糖分の摂りすぎになります。あくまで「楽しみとして」位置づけ、水分補給とは切り分ける意識が大切です。
特に成長期の子どもや受験生は、のどの渇きと同時に「甘いものを欲する」傾向があります。
だからこそ、家庭での飲み物は「味つき=当たり前」ではなく、麦茶や水筒に入れた無糖ハーブティーなど、砂糖のない飲み物に慣れる環境づくりが大切です。
このように、「何を飲むか」だけでなく「いつ、どれくらい、何の目的で飲むか」という視点を持つことが、ペットボトル症候群のリスクを遠ざける第一歩です。


飲み物の選び方を見直すことは第一歩ですが、それだけでは不十分なこともあります。
実は、水分補給の内容だけでなく、食事や間食のタイミング・質といった“生活全体のリズム”も、ペットボトル症候群のリスクに関わっています。
習慣を整えることがカギ|飲み物だけに頼らない工夫
飲み物の種類や量だけでなく、日々の食生活や間食の習慣も血糖バランスや疲労感に大きく影響します。
特に成長期のお子さんや、勉強・部活で多忙な学生には、飲み物に頼りがちなライフスタイルを「食とセット」で整える視点を大切にしましょう。
以下は、毎日の生活で取り入れやすい工夫の一例です。
✅朝食をしっかり摂る(飲み物だけで済ませない)
朝は血糖値が低く、エネルギー不足に陥りやすい時間帯。ジュースやミルクティーだけでは脳も体もフル稼働できません。主食+たんぱく質+水分の組み合わせが理想です。
例:ごはん+卵+味噌汁+麦茶
✅小腹が空いたら、飲み物でごまかさず“軽食”でエネルギー補給を
「なんとなく甘い飲み物で済ませる」が続くと、血糖が乱れやすくなります。食物繊維やたんぱく質を含む軽食を選ぶと、満足感が続きやすく間食過多も防げます。
例:ゆで卵・バナナ・小さめおにぎり・ナッツなど
✅勉強中や部活の前後は“食べ物+水分”が基本
「頑張る前にとりあえず飲む」ではなく、「軽く何かを食べて+水や麦茶で水分補給」が理想。食べ物が入っていることで、飲み物の吸収も安定します。
例:おにぎり+麦茶、バナナ+無糖ヨーグルト+水など
✅強いのどの渇きがあるときは、まずは水を少しずつこまめに摂る
一気飲みせず、体内に吸収されやすい量(1回あたり100〜150ml程度)をこまめにがポイント。冷たすぎない常温水や麦茶がおすすめです。
「忙しいから飲み物だけでいいや」と済ませるのではなく、“簡単でも体にやさしい習慣”を選ぶことが、体調を整え、集中力や持久力にもつながっていきます。
ここが知りたい!ペットボトル症候群Q&A

ゼロカロリー飲料なら安心ですか?

カロリーはゼロでも、飲みすぎには注意が必要です。ゼロカロリー飲料の多くには、アスパルテームやスクラロースといった人工甘味料が使われています。甘味に慣れすぎると「水や麦茶が物足りない」と感じ、“甘さ依存”が強くなるリスクも出てきます。
人工甘味料は、日本でも使用が認められており、適量であれば安全性に大きな問題はないとされていますが、
「ゼロカロリー=健康に良い」と思い込まず、あくまで嗜好品としてたまに取り入れる程度に留めましょう。
ゼロカロリー飲料は、どうしても甘いものが飲みたいときに“たまに”取り入れる程度にとどめ、普段の水分補給は無糖の天然飲料(水、麦茶、ハーブティーなど)を基本にしましょう。

子どもでもペットボトル症候群になりますか?

はい、誰にでも起こり得ます。体がまだ発達途中にある成長期のお子さんは、代謝のコントロール機能が未熟なうえ、ジュースやスポーツドリンクを習慣化してしまうと、依存性が高くなる傾向にあります。
特に部活後などで「水分=スポドリ」という意識が根づいていると、知らないうちに1日1L以上もの糖分入り飲料を摂取していることも。これは大人より体格が小さい分、影響も大きくなります。
水や麦茶を基本とした“水分補給の教育”も、家庭でできる健康管理のひとつです。

水分補給は1日どれくらいが目安なのでしょうか?

一般的には1日1.2〜1.5Lが目安ですが、活動量や発汗量によって調整が必要です。
夏は汗によって体内の水分と電解質(塩分やカリウムなど)が失われます。
そのため、こまめな水分摂取に加えて、塩分を適度に含む食事や、ナトリウム補給ができる飲料(経口補水液など)を活用することが重要です。
ただし、発汗による脱水を「ジュースで補う」ことは避けるべきです。糖分過多になり、逆にのどが渇く、血糖値が乱れるなどの悪循環につながります。
まとめ|飲み物の選び方が体調管理の第一歩
ペットボトル症候群は、特別な病気ではなく「誰にでも起こりうる体調の崩れ」です。
毎日の水分補給を見直すだけでも、体のだるさや不調が和らぐきっかけになります。まずは、冷蔵庫に入っている飲み物から変えてみませんか?
Blossom食と暮らしでは、日々の小さな習慣の積み重ねが未来の健康をつくると考えています。もし「うちの子どもも大丈夫かな?」「日常の食生活が心配…」など不安があれば、お問い合わせフォームよりご連絡ください。一緒に身体と心を整えるお手伝いができれば嬉しいです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました✨
こちらもチェック
- Blossomの大切にしている想いについて、詳しくはこちらをご覧ください
- Blossomのコンセプト Blossomの具体的な取り組みはこちらから
- ワークス