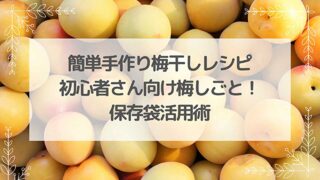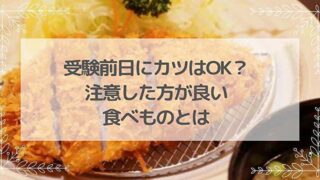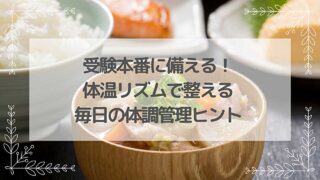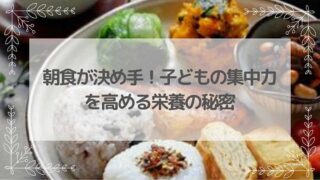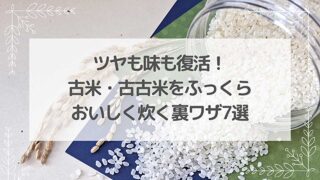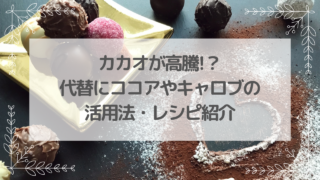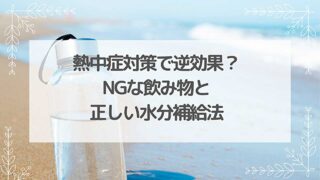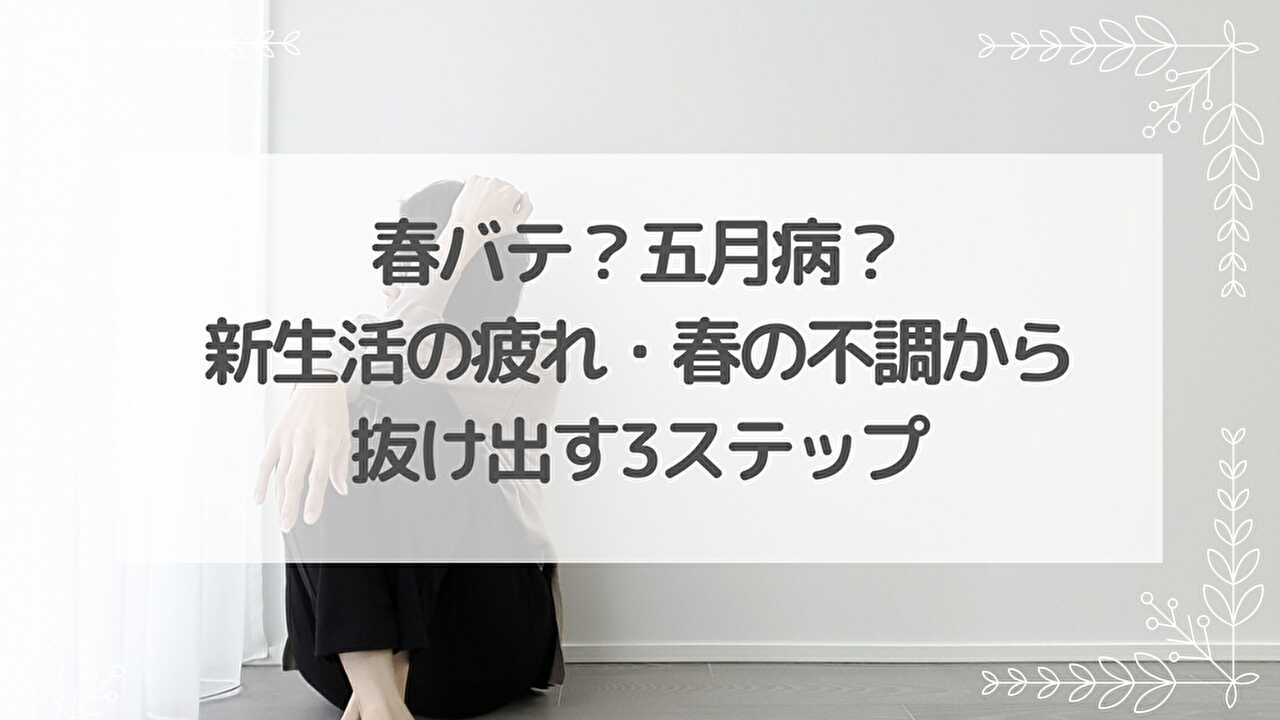こんにちは!
新年度が始まり、4月を駆け抜け気づけば5月。
環境の変化、新しい人間関係、慣れないリズム…最初は気を張っていたけれど、少し緩んだ今、「なんとなく元気が出ない」「だるい」「朝がつらい」――そんな不調を感じていませんか?

そうなんです。新生活にも慣れてきたはずなのに…なんだか最近、身体がだるかったり重かったり・・。気持ちは前向きなのですが・・。

わかりますよ。春って嬉しい変化も多いけど、実は心も身体も頑張り過ぎて疲れや不調が出やすい時期なんです。
それは“怠け”じゃなく、“がんばってきた証拠”。この時期特有の不調は、「春バテ」や「五月病」と呼ばれることもあります。
今回は管理栄養士の視点から、“なんとなく不調”をやさしく抜け出すための3つのステップをご紹介します。
GW中は家族での外出や部活の試合や大会、そしてGWが終わるとすぐに定期テストがあるなど、目まぐるしいスケジュールだと思いますが、食生活や日々の暮らしをほんの少し見直すヒントをお届けしますね。
春の不調が起きやすいのはなぜ?
春は一見、気候も穏やかで過ごしやすい季節に思えますが、頑張らなくちゃ…と気を張っていたのに、なんだか最近ぼんやりする、気持ちが重たい、朝がつらい――そんな不調を感じる理由には、実は心と身体には負担のかかりやすい時期だからということがあげられます。
それは、環境や身体の変化にがんばって対応してきた証ともいえるもの。では、なぜ不調が起こるのでしょうか?
環境の変化によるストレス
新学期や新生活・異動やクラス替えなど春は「変化」が多い時期で、たとえ前向きな変化であっても、人は無意識のうちにストレスを感じます。
ワクワクする反面、知らず知らずのうちに気を張る場面が増え、心が疲れてしまうこともあります。
気温差・気圧差による自律神経の乱れ
春は意外にも1日の寒暖差が大きく、気圧の変化も激しい季節です。
入学式が大荒れの天気だったり、冷え込んだりした経験をされたこともあるでしょう。
こうした急な変化に対応しようと、自律神経がフル稼働することでバランスが崩れ、倦怠感・頭痛・眠気・気分の落ち込みなどが起こりやすくなります。
食事や睡眠リズムの乱れ
忙しさや疲れから朝食を抜いたり、菓子パンだけで済ませてしまったりと食生活が乱れたり、栄養バランスの乱れが、エネルギー不足やメンタル不調につながることもあります。
また、シャワーだけで済ませてしまったり、質の良い睡眠がとれないと疲労感が蓄積してしまいますよね
「春バテ」「五月病」ってなに?
このような心身の変化からくる不調は、「春バテ」や「五月病」と呼ばれることがあります。
- 五月病は、特にゴールデンウィーク明けにどっと疲れが出る状態のこと。
新しい生活に気を張ってきた反動で、やる気が出ない・気分が落ち込むなどの症状があらわれます。 - 春バテは、寒暖差や生活の乱れ、自律神経の疲労によって起こる体調不良のこと。
はっきりとした病名ではなく、「なんとなく不調」を感じる春特有の状態です。
どちらも、「サボっている」「気のせい」と片づけるのではなく、“がんばってきた結果”として受け止めることが大切です。
STEP1|朝食を見直すだけで“だるさ”が軽くなる
春バテや五月病の背景には、自律神経の乱れがあります。自律神経は、生活リズムや食習慣の影響を大きく受けるため、とくに朝の過ごし方が重要です。
でも実際には…
- 「忙しくて朝ごはんを作る余裕がない」
- 「子どもがなかなか食べてくれない」
- 「自分はパンだけで済ませてしまっている」
そんなお声もよく聞きます。

実は朝食を抜いたり、菓子パンだけで済ませると、血糖値が急上昇・急降下してしまい午前中から集中力が落ちたり、栄養素不足に陥ったりすることで、余計に疲れを感じてしまうことも・・。
特に春の不調を感じやすい時期には、エネルギーや神経伝達に関わる栄養素を意識的に取り入れて、朝の体と心にスイッチを入れることが大切です。
以下の表は、春バテ・五月病対策に役立つ主な栄養素と、食品例をまとめたものです。
| 栄養素 | 働き | 多く含まれる食品 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 疲労回復・神経の安定にも 必要な栄養素 |
肉・魚・卵 大豆製品・乳製品 |
| ビタミンB1 | 糖質のエネルギー変換を助ける | 豚肉、玄米、納豆、豆腐 |
| ビタミンC | ストレスの緩和 免疫力のサポート |
ブロッコリー・ピーマン いちご・柑橘類 |
| トリプトファン | セロトニン生成を助ける (心の安定に関与) |
バナナ・牛乳・卵 ナッツ類・鶏むね肉 |
| 鉄 | 酸素運搬t・倦怠感 めまい対策 |
レバー・赤身の肉 ほうれん草・ひじき |
大切なのは“完璧”を目指すことではなく、「できることからやってみる」ことから始めてみましょう!
朝におすすめな組み合わせ例
- ご飯+納豆+小松菜のみそ汁
- トースト+卵+ブロッコリーのサラダ
- おにぎり+ゆで卵+キウイ or バナナ
頑張り過ぎず、“ちょい足し”や“温めるだけ”の工夫で、体にエネルギーが入ると朝のスイッチが入りやすくなり、気持ちにも身体にも余裕をもたらしてくれます。
STEP2|“うまくやらなきゃ”のストレスに心をほどく食の工夫を
新生活に慣れようと頑張るあまり、「もっとちゃんとやらなきゃ」と自分にプレッシャーをかけてしまうこと、ありませんか?
こうした思考のクセがストレスとなって、自律神経や消化機能にも影響を及ぼします。

実はストレスと食欲はつながっていて、イライラや不安を感じると無意識に甘いものやジャンクフードを選んでしまうことも…。
けれど、こうした“食の選び方”も少し意識するだけで、気持ちに余裕が生まれてきます。
たとえば…
✅ 心の安定に関わるトリプトファンは、バナナ・ナッツ・牛乳などに多く含まれます。
✅ ビタミンB₆(鮭・まぐろなど)やマグネシウム(納豆・豆類)もストレス対応に◎。
✅ 甘いお菓子の代わりに、ナッツやチーズを“気分安定おやつ”として取り入れてみてください。
食事は“自分をゆるめる”ための味方になります。
無理せず、ストレスを溜めない食べ方を選ぶことが、心を軽くする第一歩です。
栄養の基礎を知りたい方は、こちらの記事もチェック!
STEP3|小さな不調を放置せず暮らしの中で少しの休息を
「疲れているけど、まだがんばれる気がする」
「眠ってもスッキリしないけど、みんな同じだし…」
そんなふうに、“小さな不調”を後回しにしてしまうこと、ありませんか?
でも、それを見過ごすほど、心も体もどんどん回復に時間がかかってしまいます。
暮らしの中でできる簡単な工夫こそ、不調をこじらせないためのカギ。
たとえば…
- 夜はぬるめのお風呂に10分だけつかる(交感神経をOFFに)
- 朝は窓を開けて光を浴びながら、温かい飲み物を(体内時計リセット)
不調に気づいたら、“がんばる”よりも“整える”。
毎日の暮らしの中で、ほんの少しの食と休息の見直しが心身の疲れから抜け出す助けになります。
まとめ|“抜け出すため”には自分をいたわることから
春の不調は頑張っている人ほど、気づかないうちに無理をしてしまい、春バテや五月病につながる可能性がでてきます。

特にゴールデンウィーク明けは疲れや不調が出やすい時期。ご自身や家族の調子に少し目を向けてみましょう。
今日から始められる、小さな3つのステップ。
- 朝食のリズムを整えエネルギーをチャージ
- 不足気味な栄養素を補給してみる
- 小さな不調をそのままにせず暮らしの中で工夫してみる
春は心も体も揺らぎやすい季節だからこそ、食事や生活リズムを少し見直すことは、元気を取り戻すための確かな一歩になります。
小さな工夫からでも十分です。もし今が少し疲れてしまっていたら、無理なく、できることから始めていきましょう。
日々の積み重ねが、気づけば体調や気分を整え、新しい季節を心地よく過ごす土台になっていきます。
「体調が気になるけど、何から始めたらいいか分からない…」そんなときは、お気軽にご相談ください。
管理栄養士が、あなたとご家族に合った食生活のヒントを一緒に考えます。
👉[お問い合わせはこちらから]
こちらもチェック
- Blossomの大切にしている想いについて、詳しくはこちらをご覧ください
- Blossomのコンセプト Blossomの具体的な取り組みはこちらから
- ワークス
※不調が長く続いたり、日常生活に支障が出るほどつらいときは、無理をせず医療機関に相談しましょう。専門のサポートを受けることも大切な一歩です。