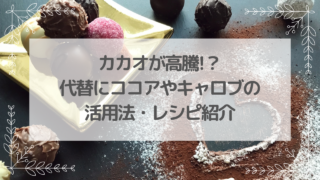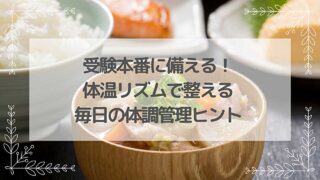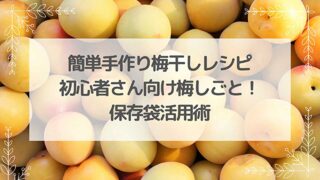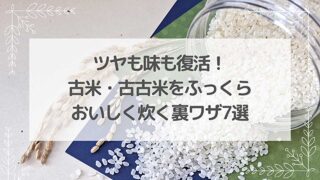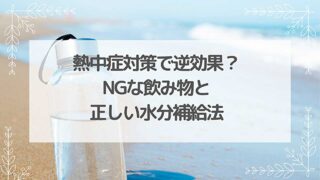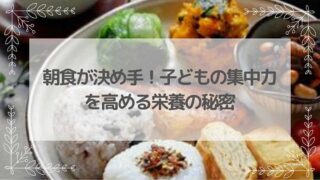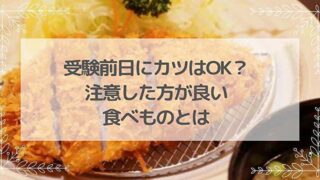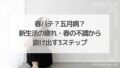こんにちは!

春は進学や新生活、職場環境の変化などで、なんだか心も体も落ち着かないですよね・・。

実はこうした季節の変わり目やストレスは、睡眠の質にも大きく影響を与えています。
前回の記事『春休みの生活リズム崩れに睡眠リセット』では、親子で取り組める生活改善のポイントをご紹介しましたが、今回はその続編として、「食事から整える快眠」について掘り下げていきます。
睡眠の質とホルモンと食生活の関係とは?
「夜眠れない」「寝つきが悪い」「途中で何度も目が覚める」…
そんな睡眠の悩みが続くと、日中の集中力や気分、体調にも影響が出てきますよね。
実は、質のよい眠りをつくるには、生活リズムだけでなく“何をどう食べるか”も大きなカギになります。
睡眠ホルモン「メラトニン」は食べ物から始まっている
深い眠りを促してくれるホルモン「メラトニン」は、体の中で自然に作られていますが、
その材料になるのは、食事から摂る「トリプトファン」という必須アミノ酸です。
● トリプトファンはまず、脳の中で“セロトニン”という神経伝達物質に変化します。
● セロトニンは「しあわせホルモン」とも呼ばれ、気分を安定させたり、自律神経を整えたりする働きがあります。
● そして夜になると、そのセロトニンが「メラトニン」に変化し、スムーズな入眠の手助けとなります。
この流れがスムーズに働いていると、日中は元気に活動できて、夜は自然と眠くなるという理想的なリズムが保てます。
ストレスや不規則な生活が続いたり、栄養が不足すると、セロトニンの分泌が減ってしまい、メラトニンも十分につくられなくなってしまいます。
栄養は「チーム」で働いている
さらに大切なのは、トリプトファンさえ摂ればOKというわけではないこと。
トリプトファンがセロトニン・メラトニンへ変わる過程では、
ビタミンB6・マグネシウム・鉄分・炭水化物などのサポートが必要です。

栄養素は、それぞれが“チームプレー”で働いているからこそ、バランスのとれた食事が睡眠の質にもつながっていきます。
睡眠の質に関わる栄養素一覧とおすすめな食べ物・飲み物
以下の栄養素は、睡眠の質を高めるうえでとても大切なものと、どんな働きがあり、どんな食材から摂れるのかを表にまとめました。
無理のない範囲で取り入れてみてくださいね。
| 栄養素 | 主な働き | 多く含む食べもの例 |
|---|---|---|
| トリプトファン | 睡眠ホルモン「メラトニン」の 材料になるアミノ酸 | 豆腐・納豆・バナナ 乳製品・卵・ナッツ類 |
| ビタミンB6 | トリプトファンから セロトニン・メラトニンを 合成する補酵素 | 鮭・まぐろ・鶏むね肉 バナナ・さつまいも |
| マグネシウム | 神経の興奮を抑えて リラックスを促す | アーモンド・ほうれん草 納豆・玄米 |
| カルシウム | メラトニンの分泌を助ける 神経の安定に関与 | 牛乳・小松菜 干しえび・チーズ |
| 鉄分 | セロトニンの合成に関与 不足すると眠りが 浅くなることも | レバー・赤身肉・ひじき あさり・大豆製品 |
| 亜鉛 | メラトニン合成を 助けるミネラル | 牡蠣・牛肉・納豆 カシューナッツ |
| オメガ3脂肪酸 | セロトニンの分泌を促進し うつ・不眠をサポート | 青魚 (さば・いわし・サーモン) |
| GABA | 自律神経を整える リラックス作用 | 発芽玄米・トマト カカオ・じゃがいも |
トリプトファンを効率よく摂る食べ方

トリプトファンは「セロトニン(しあわせホルモン)」の材料となり、さらに夜には「メラトニン(眠気ホルモン)」に変換されるので、摂るタイミングも大切です。
この変換がスムーズに行われるには、次のようなポイントを押さえておくことが大切です。
- 朝食で摂るのがベスト! 太陽の光とともにセロトニンが活性化されやすい
- ビタミンB6を含む食材と一緒に摂る(例:バナナ+ツナサンド)
- 炭水化物をセットで摂ると吸収がスムーズに
- 寝る直前のカフェイン・アルコール・暴飲暴食は避ける
✅快眠におすすめの飲み物・食べ物
就寝前や朝の時間帯にぴったりの、体と心を整える飲み物・食べ物を紹介します。
🌙 夜におすすめ
- ホットミルク(カルシウム+トリプトファン)
- 豆乳バナナスムージー
- カモミールティー(ノンカフェインハーブ)
- 温野菜スープや具だくさん味噌汁(消化の良い軽食)
🌞 朝におすすめ
- 卵×玄米ごはん+味噌汁+納豆
- ヨーグルト+バナナ+はちみつ
- サンドイッチ(ツナ・チーズ)+牛乳
成長期の子どもにとって睡眠は“栄養”

子どもの身長が伸びる・筋肉が育つ・疲れがとれる——これらすべてに深く関わっているのが「成長ホルモン」です。この成長ホルモン、実は眠っている間に最も多く分泌されることが知られています。
特に分泌が活発になるのは、深いノンレム睡眠のタイミング。つまり、夜の早い時間にしっかり深く眠れているかどうかが、発育に大きく影響しているのです。
✅ 成長ホルモンと睡眠の関係
- 分泌のピークは夜10時〜深夜2時ごろ
- ぐっすり深い眠り(ノンレム睡眠)が大切
- 睡眠中に分泌される成長ホルモンは以下の働きを担っています
| 働き | 内容 |
|---|---|
| 成長を促す | 骨の成長板を刺激し 身長を伸ばすサポート |
| 筋肉を作る | 成長とともに 筋肉の合成も促進 |
| 疲労回復 | 疲れた体を修復し 元気に動けるようにする |
| 免疫を整える | ウイルスや病気への 抵抗力を支える |
我が家の実体験から
我が家の長男も中学時代から「夜は10時前には寝る」が習慣でした。スマホやテレビは早めに切り上げ、朝は朝日を浴びてリズムを整える。特別なことはしていませんが、毎日の積み重ねが成長にしっかりつながっていたのだと、今になって実感しています。
高校卒業時には180cm超えるまでに成長し、難関大学にも無事合格しました。中学2年生の次男も、伸び盛りで現在170㎝近くあります。睡眠は、学力や集中力、そして心身の発育すべてのベースになると、改めて感じています。
「うちの子、背が伸びなくて…」「最近疲れやすくて…」そんなときこそ、食生活と睡眠を見直してみてくださいね。
成長ホルモンは、薬でも栄養ドリンクでもなく、毎晩の深い眠りの中で育まれる栄養そのものです。
まとめ|食生活や生活習慣を見直して“ぐっすり体質”に
新年度は、緊張や期待、不安など、心も体も敏感になりがちな時期です。そんなときこそ、”ぐっすり眠れる身体”を食事でつくっておくことが大切です。
眠りの質が高まれば、日中のパフォーマンスや体調、気分まで変わってきます。
まずは普段の食事から整える——その一歩が、あなたやご家族の心地よい睡眠につながっていきます。
📌この記事はブックマークしていただけると、春の睡眠や食生活を見直したいときにきっと役立ちます♪
気になることやご相談等ありましたら、[お問い合わせページ]からメッセージをいただけると嬉しいです。
またブログにも、体と心を整えるヒントを発信していきますので、どうぞごゆっくりご覧くださいね。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
こちらもチェック
- Blossomの大切にしている想いについて、詳しくはこちらをご覧ください
- Blossomのコンセプト Blossomの具体的な取り組みはこちらから
- ワークス
📚 参考資料一覧(2025年4月閲覧)
※この情報は一般的な健康管理を目的とした内容であり、医療行為や診断を目的としたものではありません。睡眠障害が長く続く場合は医師や専門家にご相談ください。