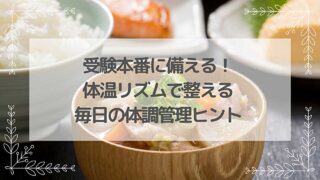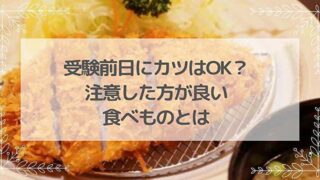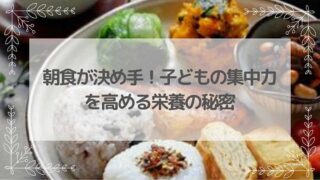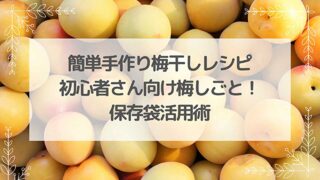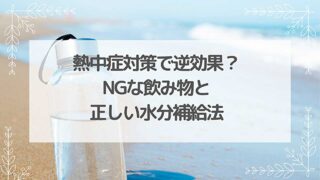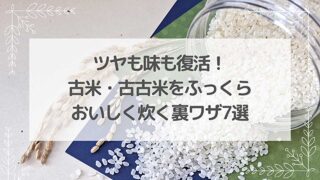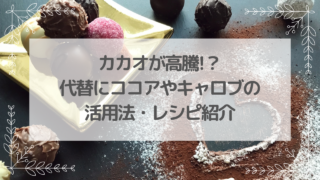こんにちは!
異様な暑さが続いていますが、この季節は特に気をつけたいのは食中毒ですね。

家で私たちが食中毒に関して具体的に何に注意をすればいいのか、わからないです。冷房つけてるから、家の中は安全だと思ってました。

それが落とし穴で、実はキッチンでの”いつもの習慣”が原因になることも・・。実は6〜8月は、1年でもっとも食中毒が起こりやすい季節です。
この記事では、厚生労働省や農林水産省も提唱している「食中毒予防の三原則」を、家庭で無理なく実践するためのポイントを、管理栄養士の視点からお伝えします。
食中毒が増える季節|梅雨から夏が特に危険な理由

気温と湿度が高い6月〜8月は、細菌が増殖しやすい条件が揃っています。冷房が効いていても、キッチンや弁当の中の温度や環境によってはリスクがあることも多く、見た目では判断できないケースがあります。
また、雨で湿気がこもりやすく、台所の換気が不十分になることも細菌の繁殖を助けてしまいます。
とくに作り置きや常備菜、お弁当などを多く作る家庭では、ほんの少しの油断が事故につながる可能性もあるのです。
次に、家庭内でも見逃せない原因菌の特徴を見ておきましょう。
よくある原因菌とその特徴
- カンピロバクター:生焼けの鶏肉に多く、少量でも感染。
- サルモネラ菌:卵や肉類から。半熟卵は注意。
- 黄色ブドウ球菌:手指の傷や皮膚から食品へ移る。
- ウェルシュ菌:カレーや煮物などで室温放置により増殖。
これらの菌は家庭内でも簡単に広がるため、衛生習慣の見直しが欠かせません。
こうした菌は、調理中だけでなく、食材の保存方法や手洗いの不備からも入り込みます。
だからこそ、次に紹介する「食中毒を防ぐ三原則」を日々の生活に取り入れることが重要です。
食中毒を防ぐ3原則とは?
✅【つけない】菌を持ち込まない・広げない
菌の侵入を防ぐには、まずは手洗いと清潔な調理環境が基本です。
- 調理前・後・肉や魚を触った後は石けんでしっかり手を洗う
- 布タオルの共用は避け、ペーパータオルやこまめに交換する布巾を使う
- 肉や魚を切った包丁・まな板はその都度洗い、用途別に使い分けると安心です
また、買ってきた肉のトレーから出るドリップ(肉汁)にも菌が含まれているため、調理中は周囲に飛び散らないよう注意し、触ったらすぐに手を洗うことが大切です。
✅【増やさない】菌を増殖させない
菌は時間とともに増えていきます。だからこそ、調理後はなるべく早く冷却・保存しましょう。
- カレーや煮物など、大量に作る料理は浅く広げて粗熱を取り、すばやく冷蔵庫へ
- できればフライパンやバットに広げて冷ます→小分け→冷凍庫保存という流れが安心です
- お弁当用のおかずは、小分けして冷凍すれば衛生的で便利です
- ちくわやチーズなどの要冷蔵食材は、加熱してから入れることでリスク軽減になります
このように、作るだけでなく「冷ます・保存する」ことも調理の一部。ちょっとした工夫で菌の増殖を防ぐことができます。
✅【やっつける】しっかり加熱・殺菌
多くの菌は加熱によって死滅します。食材の中心までしっかり火を通すことが基本です。
- 肉や魚の加熱は75℃以上で1分以上が目安
- 電子レンジを使うときは加熱ムラが出やすいので、かき混ぜたり耐熱皿に広げたりして調整を
- 弁当箱や水筒などは、使用前に熱湯をかける・酢で拭くなどで簡易的な殺菌を
菌に対して”最後の一手”となるのがこの「やっつける」工程。日々の調理にしっかり組み込みましょう。
それでは、具体的にどんなところに気をつければいいのか、家庭でのポイントを見ていきましょう。
家庭でできる衛生習慣の見直しポイント
夏場のお弁当は、朝つくってから食べるまでの時間が長くなるため、とくに注意が必要です。
お弁当で注意したいこと
- ミニトマトはヘタを取って水分を拭き取ることで腐敗を防ぎます
- レタスなどの葉物で仕切ると水分が出やすいので、バランやシリコンカップを活用すると衛生的
- ポテトサラダやマカロニサラダなどは、冷ましたあとにしっかり密閉して詰めるようにします
- 汁気のある煮物は避けるのが基本です

汁気がある煮物などをお弁当にどうしても入れたい場合の工夫をまとめてみましたので、参考にしてみてくださいね。
✅汁気のある煮物をお弁当に入れるときの工夫
| 方法 | メリット | 注意点・補足 |
|---|---|---|
| 鰹節・とろろ昆布を敷く (和風の場合) | ・自然に汁気を吸収 ・食べられる ・風味アップ | ・塩分がやや高めなので量に注意 ・味の相性を確認 |
| 寒天やゼラチンで固める (洋風の場合) | ・煮汁を閉じ込めて汁漏れ防止 ・見た目もきれい | ・手間がかかる ・味との相性に注意 |
| シリコンカップ | ・外側のカップが汁を吸収 ・仕切りにもなる | ・量やサイズに注意 ・水分が多いと完全には防げない |
| 冷ましてから汁気をとる(ふき取り) | ・準備不要で基本的な対策 ・どんなおかずにも応用可能 | ・十分に冷ます必要あり ・拭き残しに注意 |



また、お弁当箱自体の清潔も大切。見落としがちなフタのパッキン部分は雑菌が残りやすい場所なので、こまめに取り外して洗うのがおすすめです。
さらに、意外と見落としがちなのが飲み物の管理。とくに暑い時期は、口をつけたペットボトルを常温で放置するのはNG。
口の中の雑菌が飲み口から逆流し、時間が経つと菌が増えてしまう可能性があります。こまめに飲み切るか、直接口をつけない方法を取りましょう。
調理後〜保存の工夫
「一晩寝かせたカレーはおいしい」と言われることもありますが、常温で放置するとウェルシュ菌の温床になりかねません。
- カレーは調理後すぐに火から下ろし、バットなどに広げて素早く冷ます
- 十分に冷めたらジップロックや保存容器に小分けして冷凍庫へ
- 解凍・再加熱の際も中心までしっかり加熱することが大切です
「冷ます→保存する」という工程は、どの家庭でもできる立派な予防策です。
キッチンまわりも定期チェック
- 食器用スポンジは3日〜1週間で交換または漂白・熱湯消毒を
- ふきんや布巾も、使いっぱなしにせず、小まめに洗ったり煮沸消毒で清潔をキープ
- 調味料のフタや冷蔵庫の持ち手など、手が触れる場所を拭き掃除する習慣をつけましょう
こうした”小さな手間”の積み重ねが、家族の健康を守る大きな力になります。
それでも万が一、体調に異変を感じたときは、以下のように対応しましょう。
もし食中毒が起きてしまったら
- 吐き気・下痢・腹痛・発熱などの症状が出た場合は無理せず、安静に過ごすことが大切です
- 脱水対策としての水分補給はこまめに。可能であれば経口補水液やスポーツドリンク、ゼリー飲料を利用しましょう
- 自己判断で下痢止めや吐き気止めを使うと、体外に排出すべき菌がとどまってしまう可能性があります
- 症状が長引く、または改善しない場合は早めに医療機関を受診しましょう


ここが知りたい夏の食中毒対策Q&A

一晩寝かせたカレーが美味しいといいますが、やっぱり危険なのでしょうか?

はい。ウェルシュ菌が繁殖するリスクがあります。常温での長時間放置は避け、素早く冷まして小分け冷凍がおすすめです。
時間がない時は、 バットに広げて保冷剤をのせる⇒氷水を張った鍋に容器ごと入れる⇒扇風機で風を当てるなどして、冷めたら即冷凍すると良いでしょう。

お弁当にミニトマトを入れてもいいですか?

ヘタを取り、水分をしっかり拭いてからにしましょう。

食中毒って、どこが一番リスクが高いんですか?

実は「家庭のキッチン」です。とくに生肉を触った後の手や調理器具、そしてスポンジ・ふきんなどの“湿った環境”に菌が繁殖しやすくなります。食品より「手と道具の管理」がカギです。

子どもや高齢者、免疫力が下がっている人は、やっぱり食中毒のリスクが高いのですか?

はい。子どもや高齢者、そして体調不良や治療中などで免疫力が落ちている方は、食中毒にかかると症状が重くなりやすく、回復にも時間がかかることがあります。
とくにお弁当では「常温で放置しない」「必ず加熱済みのものだけを詰める」といった配慮が大切です。
そして、しっかり冷まして、保冷して持参しましょう。
ちょっとした油断が重い体調不良につながることもあるため、慎重すぎるくらいが安心です。
まとめ|家庭でできる“安心”はキッチンから始まる
ちょっとした疑問から気づくことがたくさんあります。忙しい毎日の中でも、手洗いや保存、加熱などの習慣を少し見直すだけで、家族の健康を守ることができます。
「Blossom 食と暮らし」では、こうした季節の暮らしに役立つ情報を、管理栄養士の視点でわかりやすく発信しています。
暮らしと未来を守る「食」のヒントを、これからもお届けしていきますので、ぜひ他の記事でも食と暮らしを整えるヒントにしてくださいね。
ご感想・ご質問はHPのお問い合わせフォームから、お気軽にご連絡ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました✨
こちらもチェック
- Blossomの大切にしている想いについて、詳しくはこちらをご覧ください
- Blossomのコンセプト Blossomの具体的な取り組みはこちらから
- ワークス