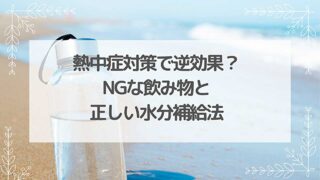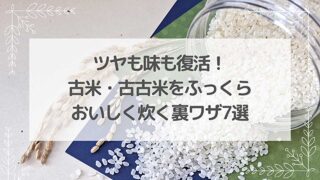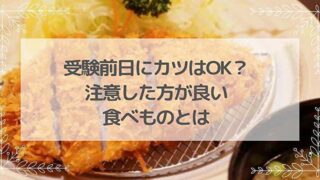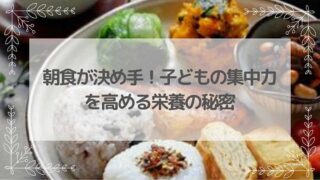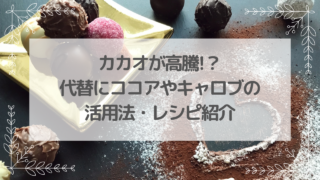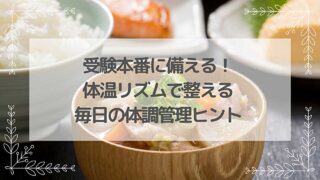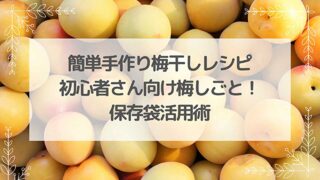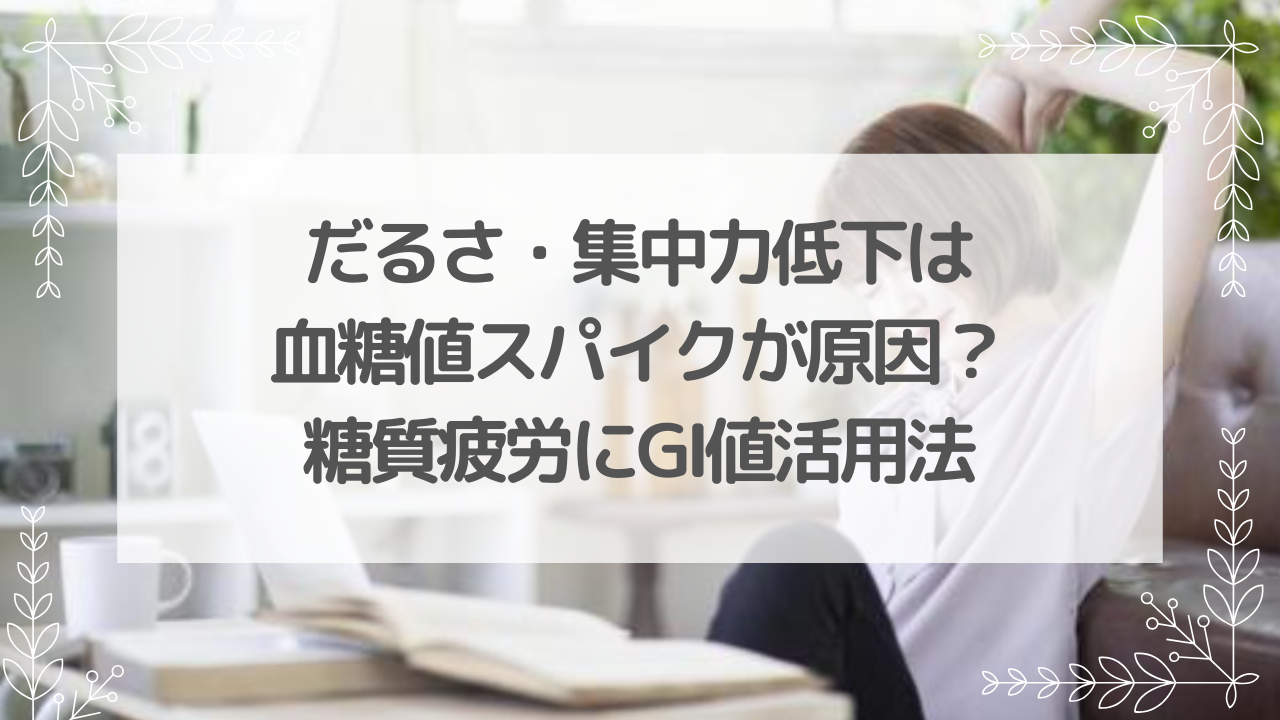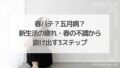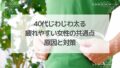こんにちは!
「なんだか疲れやすい」「夕方になるとどっと疲れが出る」──そんな声をよく聞くことがあります。

食生活に気を付け始めているのですが、だるさや疲れやすさ、集中力が続かないことあります。

「それでも疲れやすい…」と感じている方は、もしかすると“糖質の摂り方”が関係しているかもしれません。
これまでの記事では、五大栄養素や抗酸化成分、食事バランスについてもお話してきましたが、「何かが足りない」「まだ不調が続く」と感じる方にこそ、特に注目したいのは、「糖質(炭水化物)」の摂り方です。
「疲れやすさ」や「集中力の低下」には、血糖値の乱高下が関係していることがあり、「エネルギー源である糖質の摂り方」によって、身体と心のパフォーマンスに差が出ることも・・。
今回は、血糖値スパイクと糖質疲労の関係、そしてGI値を活用した食生活改善ポイントについてご紹介します。
血糖値スパイクと糖質疲労|だるさ・集中力低下の意外な理由
「なんだか最近、疲れやすい」「午後になると集中できない」・・そんな体のサイン、見逃していませんか?
それは、単なる寝不足や加齢・体質のせいではなく、「血糖値の乱高下」が関係しているかもしれません。特に40代以降の女性や成長期のお子さんは、ホルモンバランスや生活リズムの変化も加わり、体が血糖値の影響を受けやすくなっています。
ここでは、「血糖値スパイク」と「糖質疲労」というキーワードから、疲れやすさの背景にある仕組みを紐解きます。
血糖値の乱高下で起こる不調とエネルギー切れ
糖質の多い食べ物により血糖値が急激に上昇し、その後インスリンの過剰な働きで急降下する状態を「血糖値スパイク」ということがあります。
この血糖値の急なアップダウンにより、身体や脳は一時的にエネルギー切れのような状態に陥り、次のような不調を感じやすくなります。
✅食後すぐ(血糖値が急上昇)
- 一時的に元気が出たように感じる
- 気分が高まり、満足感がある
- 甘いものを食べたことで、脳が一瞬“シャキッ”とする
✅1〜2時間後(血糖値が急降下)
- 強い眠気に襲われる
- 頭がぼんやりして集中できない
- 体がだるく感じる
- 甘いものがまた欲しくなる(間食への欲求)
✅さらに続く影響
- イライラしやすく、情緒が不安定になる
- 気分が落ち込みやすくなる
- 「食べたのに疲れが取れない」と感じる
こうした状態を、近年では「糖質疲労」という言葉で表すこともあります。「血糖値スパイク」や「糖質疲労」は医学用語ではなく血糖値の乱高下により“食べても疲れる”状態を表現した健康ワードのひとつです。
※あくまで生活習慣に関わる傾向の一つであり、医師による診断が必要なケースもあります。不調が長引く場合は医療機関への相談をおすすめします。

特に、朝食や昼食に菓子パンや白米だけを食べるといった糖質の過剰摂取や血糖値の乱高下に伴うエネルギーの不安定さからくるものと考えられています。この血糖値のジェットコースターのような動きが、脳と体を振り回し、結果的に「疲れた」と感じやすくなる要因のひとつとなります。
これらは単なる“気のせい”ではなく、血糖値の動きが脳の働きや自律神経に影響している可能性もあり、大人だけでなく、子どもにも起きることがあるため注意が必要です。。
親世代である私たちも、「自分が疲れているのは歳のせい」と思い込まず、日々の食事内容を見直すことで、体の“エネルギーリズム”を取り戻すヒントが見えてくるかもしれません。
糖質・炭水化物・GI値の基礎知識
よく似た言葉に思われがちな「炭水化物」と「糖質」ですが、実は違いがあります。
- 炭水化物=糖質+食物繊維
- 糖質=血糖値を上げるエネルギー源
同じ炭水化物でも、食物繊維が豊富な食品は血糖値の上昇を抑えやすくなります。
では、どうすれば血糖値の乱高下を防げるのでしょうか?
GI値を活用して血糖値の乱高下をサポート
カギになるのが、GI値(グリセミック・インデックス)の活用です。
GI値とは、ある食品を食べた後に血糖値がどれくらい上昇するかを示す指標で、低いほど血糖値がゆるやかに上がる=疲れにくい体づくりをサポートすることに繋がります。
✅GI値の目安
| GI分類 | 主食系 | 果物 | 野菜・いも類 | 乳製品 |
|---|---|---|---|---|
| 高GI (70以上) |
白米 食パン 餅 菓子パン |
ジャム 缶詰フルーツ ドライマンゴー |
じゃがいも 長いも にんじん (加熱) |
練乳 ミルク飲料 (加糖) |
| 中GI (56〜69) |
玄米 もち麦ごはん コーンフレーク |
バナナ 柿 パイナップル |
かぼちゃ さつまいも |
加糖ヨーグルト アイスクリーム |
| 低GI (55以下) |
雑穀米 そば 春雨 りんご |
みかん ベリー類 グレープフルーツ レタス |
きのこ類 小松菜 ブロッコリー 無糖ヨーグルト |
牛乳 チーズ |
同じ炭水化物でも糖質量が多い食品は血糖値を上げやすく、糖質量が少なく食物繊維が多い食品は、血糖値の急上昇を抑えやすいということがわかりますね。
たとえば、白米やうどんは高糖質で血糖値を上げやすいですが、玄米や雑穀米は食物繊維が豊富でゆるやかに吸収されます。
GI値は「食後血糖値の上昇のしやすさ」に基づいた指標であり、エネルギー(カロリー)や脂質量の多さとは別に考える必要があります。

カロリーの高いものでも、GIが低い場合もあるため、目的に応じて使い分けることが大切です。栄養バランスの中でGI値を参考に一つの目安として活用しましょう。
※GI値は食べる食品単体での指標であり、調理方法や組み合わせ、食べる順番によっても変動します。情報の正確性を期すためには、信頼できるデータベース(例:シドニー大学)を参考にするのが望ましいとされています。
陥りやすい「高GI食」の落とし穴
忙しい毎日の生活の中で「つい簡単に食べられるものを選んでしまう」ことが多くなります。
以下のような食事、思い当たりませんか?
- 昼食はコンビニのおにぎりと菓子パン
- おやつに甘いスナックやスイーツ
- 夕方の疲れにチョコレートやジュースをつまむ

こうした食事は高GI食品が中心になりやすく、血糖値スパイクを招きやすい組み合わせです。
疲れやすさ・だるさ・集中力低下の一因になっている可能性があります。
実践!低GI食品の選び方と食事の工夫
GI値を意識して血糖値の急上昇を抑えるためには、以下のような工夫が有効です。
🌿低GIを意識した食事のポイント
- 白米 → 雑穀米やもち麦入りごはんに切り替える
- パン → 全粒粉パン・ライ麦パンを選ぶ
- 野菜・豆・海藻を「最初に」食べる
- たんぱく質(肉・魚・卵・大豆)と一緒に摂る
- よく噛んでゆっくり食べる
食物繊維やたんぱく質、脂質を組み合わせることで、糖の吸収がゆるやかになり、血糖値の急激な上昇を防ぐサポートになります。
食後の眠気・だるさ対策に!おすすめの低GIおやつ
疲れたときに甘いものをつまみたくなる気持ち、よくわかります。
ですが、ここで高GIのお菓子を選ぶと、また血糖値スパイクの悪循環に。
そこで、罪悪感なしで楽しめる低GIおやつをいくつかご紹介します。
🍪おすすめおやつリスト
- 無塩ナッツ(アーモンド・くるみなど)
- 高カカオチョコ(カカオ70%以上)
- ゆで卵
- プレーンヨーグルト+ベリー類
- 全粒粉クラッカー+チーズ
こうしたおやつは、血糖値を安定させながら「小腹を満たす」助けになります。

おやつ(間食)は「甘いものを我慢するかどうか」ではなく、「補食(エネルギーや栄養のサポート)」として捉えてみてください。低GIのおやつやタンパク質を含む軽食は、血糖値の安定や集中力の維持にも役立ちます。
血糖値を安定させる食生活のコツ
食後の血糖値を安定させるには、“食べる順番”や“組み合わせ”にもコツがあります。
🥗 セカンドミール効果を活用しよう
セカンドミール効果とは、1回目の食事の内容が次の食事の血糖値にも影響するので、朝食の摂り方を気を付けようという考え方です。たとえば朝食に低GI食品を摂ると、昼食後の血糖値の上昇がゆるやかになることも。
だからこそ、朝食を抜かず、できるだけ血糖を安定させる内容に朝に玄米や納豆、野菜など食物繊維を含む食事を選ぶといった意識が、次の食事の体調にもつながってきます。
🍽 食べる順番を工夫するだけでも違う!
最初に野菜や海藻、きのこなど“食物繊維”を含むものから、次にたんぱく質(肉・魚・卵・豆類など)最後に主食(ごはんやパン)
という順番にするだけで、血糖値の上昇がゆるやかになります。外食や忙しいときでも、汁物やサラダから一口でも始めると変化が期待できます。
栄養の基礎を知りたい方は、こちらの記事もチェック!
まとめ|だるさ・疲れのループを断ち切るヒントは血糖値
だるさや集中力の低下が感じた、「糖質の質」と「摂り方」を見直してみるのがおすすめです。
- 血糖値スパイクは、食後の不調(だるさ・眠気・脳疲労)の一因になることも
- GI値を意識して、糖質を“選ぶ”ことで体と心の負担を軽くすることが可能に
- 無理な制限ではなく、“賢い糖質コントロール”で疲れにくい体をサポートする

私自身も、栄養の知識があるはずなのに「なんだか疲れやすい」と感じた時期があります。がんばりすぎず、焦らず、まずはできるところから始めてみてくださいね。

40代以降はホルモンバランスの変化や生活の忙しさも重なり、「身体の声」に気づきにくいこともあるので、日々の食事にほんの少し意識を加えるだけで、ぐっと過ごしやすくなるということですね。
また、お子さんにも同じように、朝食を抜いたり甘いものに偏った食事が続くと、集中力の低下やイライラなどの影響が出ることがあります。親子で一緒に食生活を見直すことが、お互いの体調管理にもつながります。
食事や体調に関するお悩みがあれば、個別カウンセリングも行っています。無理のない方法で、一緒に体調改善のきっかけを見つけていきましょう。詳しくはお問い合わせから、ご連絡ください。
こちらもチェック
- Blossomの大切にしている想いについて、詳しくはこちらをご覧ください
- Blossomのコンセプト Blossomの具体的な取り組みはこちらから
- ワークス
📚 参考資料一覧(2025年5月閲覧)
なお、だるさや不調が長く続く場合や、生活に支障をきたすような場合は、自己判断せずに医療機関に相談されることをおすすめします。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました✨