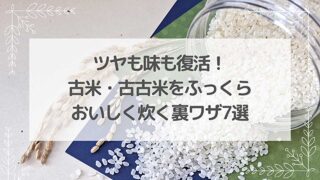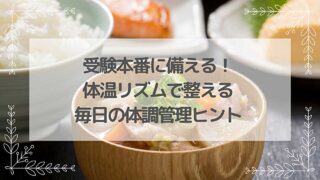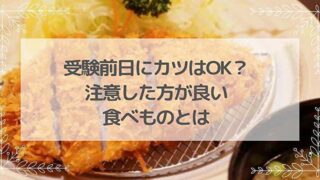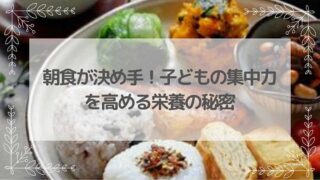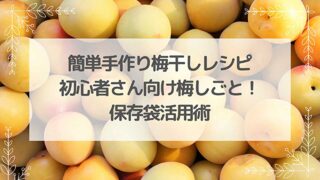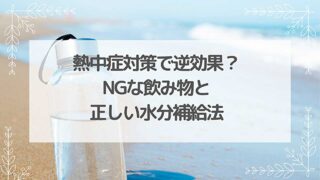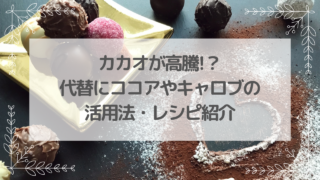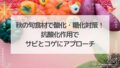こんにちは!
少し涼しくなりましたが、ニュースでは気象庁が「過去の気候とは異なる機構であるということを前提にして、社会として適応していく必要あると感じている」と発表していましたね。

夏の猛暑を乗り切ったはずなのに、朝晩涼しくなってきた今も「だるい」「疲れが抜けない」と感じることがあります・・。

実はそれ、“秋バテ”かもしれませんね。夏バテと似ていますが、原因も時期も異なるのが特徴です。
夏バテや秋バテは医学的な病名ではなく、季節の変わり目に多く見られる体調不良を指す一般的な呼び方です。
夏の疲れを残したまま急に涼しくなったり、台風による気圧の変化や日照時間の短縮が重なると、体調を崩す人が少なくありません。
本記事では、秋バテと夏バテの違い、起こりやすい時期や原因、セルフチェックリスト、自律神経を整えるための生活・栄養面から対策をわかりやすく紹介します。
秋バテと夏バテの違い
まずは両者の違いを整理してみましょう。
| 項目 | 夏バテ | 秋バテ |
|---|---|---|
| 起こりやすい時期 | 梅雨明け〜8月の盛夏 | 9月〜10月、季節の変わり目 |
| 主な原因 | 高温多湿・冷房の効きすぎ 冷たい飲食 | 気温差・気圧変化 日照時間の短縮 |
| 主な症状 | 食欲不振、下痢・胃もたれ 全身のだるさ | 休んでも疲労回復しない 眠りが浅い 頭痛・肩こり、気分の落ち込み |
| 特徴 | 暑さによる体力消耗 | 自律神経・ホルモンの乱れ |
夏バテは「暑さによる体力消耗」、秋バテは「季節変化による自律神経の乱れ」など違いがありますね。
身体の中で起きていることは別物で対策も変わってきます。
秋バテはいつ起こりやすい?主な原因
秋バテは、夏の疲れを引きずったまま季節が変わる9月〜10月に起こりやすいといわれています。特に今年のように猛暑が長引いた年は要注意です。

朝晩と日中の寒暖差や、台風による気圧変動も大きな負担になります。さらに、日照時間が短くなることで体内リズムが乱れ、疲れが抜けにくくなることが原因とされています。
では、なぜ季節が変わるだけで体調が崩れるのでしょうか?その背景にあるのが、自律神経やホルモンの乱れです。
✅秋バテの主な原因
秋バテを引き起こす大きな要因は次の3つです。
- 気温差:朝晩は冷え込むのに日中はまだ暑い → 自律神経が温度調整で疲れる
- 気圧変化:台風や秋雨前線 → 血圧や血流の変化を招き、頭痛やめまいにつながる
- 日照時間の短縮:セロトニン(幸せホルモン)が減少 → 睡眠ホルモン(メラトニン)も不足し、眠りが浅くなる
つまり、秋バテは「自律神経とホルモンの乱れ」が根本原因です。では、私たちはどんなサインで気づけばよいのでしょうか?
秋バテセルフチェックリスト
以下のチェックリストに当てはまる数が多い方は、早めに生活を整えて対策することが大切です。
- 休んでも疲れが抜けない
- 朝起きるのがつらい
- 眠りが浅い、夜中に目が覚める
- 食欲が出ない、または乱れている
- 頭痛・肩こり・関節の痛みがある
- 気分の落ち込み、集中力の低下
※「秋バテ」は医学用語や診断名ではなく、季節の変わり目に多くみられる体調不良を指す俗称です。強い頭痛や倦怠感、日常生活に支障がある場合は、自己判断せず医療機関にご相談ください。
放置すると免疫力の低下やメンタル不調につながりかねないので、日常生活の中で自律神経を整える対策は役立ちます。
秋バテ対策|自律神経を整える朝と夜の生活習慣
✅朝の習慣
- 朝日を浴びる:体内時計をリセットし、セロトニンを分泌
- 深呼吸・軽い運動:自律神経を刺激する
- 常温の水を一杯:胃腸を目覚めさせる
✅夜の習慣
- 就寝2時間前のぬるめ入浴:体温リズムを整えて眠りの質を高める
- スマホやカフェインを控える:交感神経を落ち着ける
生活リズムを整えることが第一歩ですが、食事も自律神経とホルモンの材料を補う大切な要素です。
食事でできる秋バテ対策
秋バテは自律神経やホルモンの乱れ、腸内環境の不調と深く関わっています。

何を食べるかが体調回復のカギになります。ポイントは「神経を支える脂質」「ホルモンの材料になるアミノ酸」「腸を整える食物繊維・発酵食品」「代謝に欠かせないビタミン・ミネラル」を組み合わせることです。
✅青魚(サンマ・サバ・イワシ)
サンマやサバ、イワシなどの青魚に豊富なオメガ3脂肪酸(EPA・DHA)は、脳や神経の働きを助け、気分の安定にもつながります。特に秋はサンマが旬で、栄養価も高い時期。缶詰や切り身でも手軽に摂れるので、週2回程度を目安に食卓に取り入れるのがおすすめです。
✅乳製品・大豆食品
牛乳・ヨーグルト・チーズなどの乳製品や、豆腐・納豆・豆乳などの大豆食品には、トリプトファンという必須アミノ酸が含まれています。これは「幸せホルモン」と呼ばれるセロトニンの材料となり、夜には睡眠ホルモン(メラトニン)に変わります。朝や昼に取り入れることで、夜の眠りの質が整いやすくなります。
✅発酵食品・食物繊維
腸は「第二の脳」とも呼ばれ、免疫細胞の約7割が集中していると言われています。腸内環境が乱れると免疫力が下がり、疲れも抜けにくくなります。
そこで役立つのが、発酵食品(ヨーグルト・納豆・みそ・漬物など)と食物繊維(雑穀・根菜・きのこ・海藻類)。これらを毎日の食事に少しずつ加えることで、腸内細菌のバランスが整い、秋バテ予防につながります。
✅ビタミンB群・マグネシウム
代謝を円滑に進め、神経や筋肉の働きを助けるのがビタミンB群とマグネシウムです。ビタミンB6はかつおやまぐろ、鶏むね肉、バナナに多く含まれ、トリプトファンからセロトニンを作るのを助けます。
マグネシウムは豆類・ナッツ・海藻に豊富で、神経の安定や筋肉のけいれん予防に役立ちます。
睡眠と食生活のついては、こちらの記事をご覧ください。
このように、生活習慣と食事を意識することで秋バテは予防できます。最後に、よくある疑問をQ&A形式で整理します。
ここが知りたい|秋バテQ&A

秋バテはいつからなのでしょうか。

例年9月中旬〜10月にかけて多く、猛暑の疲れが残っている年ほど感じやすい傾向にあります。

夏バテとの最大の違いは何でしょうか?

夏バテは「暑さによる体力消耗」、秋バテは「季節変化による自律神経やホルモンの乱れ」という違いがあります。

自律神経を整える一番簡単な方法はありますか?

朝の光を浴びること。数分でも効果があり、セロトニンと体内時計を整える助けになります。

食生活で意識するポイントは何でしょうか?

青魚・発酵食品・乳製品・食物繊維をバランスよく摂り、腸とホルモンの材料を満たしましょう。
※強い頭痛や日常生活に支障がある場合は「気象病」など別の疾患の可能性も。無理せず医療機関へ相談しましょう。
まとめ|秋バテを早めに見極めて日常でできる対策を
秋バテは夏バテとは異なり、気温差・気圧変化・日照不足による自律神経やホルモンの乱れが主な原因です。発症しやすいのは9〜10月で、夏の疲れをそのまま持ち越している人ほど注意が必要です。
セルフチェックリストで早めに気づき、生活リズムや食事を整えることが大切です。放置せずに小さな工夫から始めましょう。

秋は本来「食欲の秋・行楽の秋」。体を整えれば、一年で最も過ごしやすい季節を楽しめます。“整える習慣”を今日から少しずつ取り入れてみましょう。
朝の光・深呼吸・常温水、夜の入浴、腸とホルモンを支える食事を意識することが、秋バテ予防の第一歩です。
秋バテの食事や生活習慣について「自分の場合はどうしたらいいの?」と感じた方へ。
お気軽にお問い合わせフォームからご相談ください。日常のちょっとした工夫から一緒に考えましょう。
こちらもチェック
-
大切にしている想いについて、詳しくはこちらをご覧ください
- Blossomのコンセプト お仕事内容や具体的な取り組みはこちらから
- Blossomのワークス 日常や感じたことを綴るブログはこちらから
- Blossomのブログ