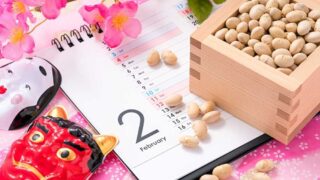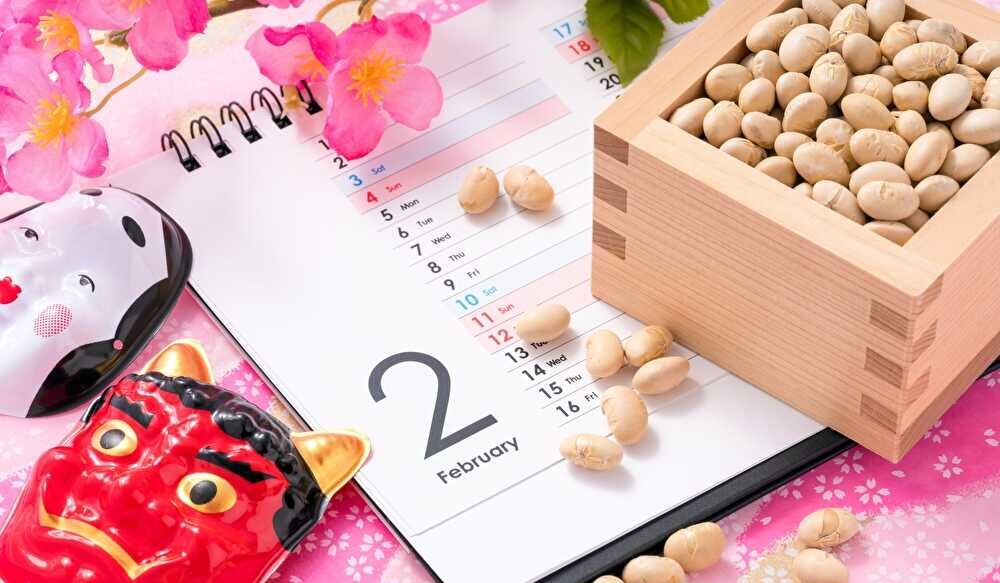こんにちは!
2月になると「節分」や「立春」という言葉をよく耳にしますが、それぞれの意味を正しく理解している人は意外と少ないかもしれません。
節分は豆まきや恵方巻のイメージが強いですが、実は季節の変わり目を意識した大切な行事です。
また、立春は旧暦では新年の始まりとされ、気持ちを新たにするタイミングでもあります。
寒暖差が大きいこの時期は、体調を崩しやすく、また受験シーズンでもあるため、身体と心を整えることが特に大切です。
今回は、節分と立春の違いや由来、食べ物、そして意識しておきたいことについてご紹介します。
立春と節分の違いとは?
節分とは
「節分」とは文字通り「季節を分ける日」という意味を持ち、もともとは立春・立夏・立秋・立冬の前日を指していました。
しかし、現在では主に「立春の前日(2月3日頃)」を指すことが一般的です。
節分には邪気を払うために豆まきをする習慣があり、「鬼は外、福は内」と唱えながら豆をまくことで、新しい季節を健やかに迎えるという願いが込められています。
立春とは
「立春」は二十四節気の一つで、暦のうえでは春の始まりとされる日です。
旧暦では立春から新しい一年が始まると考えられており、今でも「立春大吉」と書かれたお札を貼る風習が残っています。
春の訪れを感じる時期ではありますが、まだ寒さが厳しく雪が降ることもあるため、体調管理に気をつけながら徐々に春を迎える準備をしましょう。
立春・節分に食べるもの
■節分の食べもの
- 福豆(大豆):豆まきに使われる大豆には「邪気を払う」という意味があり、まいた後に年齢の数だけ食べることで健康を願います。
- いわし:焼いたいわしの匂いが鬼を寄せ付けないとされ、柊の枝にいわしの頭を刺して玄関に飾る風習もあります。
- けんちん汁:根菜たっぷりの汁物は体を温め、寒さが厳しい時期にぴったりです。
■立春の食べもの
- 七草粥:本来は1月7日に食べるものですが、立春の頃にも胃腸を整える目的で食べるのがおすすめです。
- 柑橘類(みかん・ゆず):ビタミンCが豊富で、寒暖差の激しい時期の体調管理に役立ちます。
- 発酵食品(味噌・漬物・納豆):腸内環境を整え、免疫力を高める作用が期待できます。
栄養の基礎を知りたい方は、こちらの記事もチェック!
立春・節分の時期に意識したいこと
体調管理
寒暖差が大きく、自律神経が乱れやすい時期です。冷え対策として、温かい汁物や発酵食品を積極的に取り入れましょう。
また、受験シーズンでもあるため、胃に優しい食事を意識することも大切です。
受験生の寒さ対策についてはこちらの記事を参考にしてくださいね。
冬を乗り切る健康管理のヒントをもっと知りたい方は、こちらの記事もチェック!:
心の整え方
立春は新しい一年の始まりとされるため、無理な目標を立てるのではなく、小さな「習慣」を意識してみるのがおすすめです。
節分は邪気払いの時期でもあるので、不要なものを整理し、気持ちをリセットするチャンスと捉えましょう。
まとめ
節分は「冬と春を分ける日」、立春は「春の始まり」を意味します。
この時期には、邪気を払う食材や旬の食べ物を取り入れながら、心と体を整えていくことが大切です。
日々の食事や生活習慣を少し意識するだけでも、気持ちよく新しい季節を迎えることができます。寒暖差に負けず、健やかな春を迎えましょう!
こちらもチェック
- Blossomの大切にしている想いについて、詳しくはこちらをご覧ください
- Blossomのコンセプト Blossomの具体的な取り組みはこちらから
- ワークス