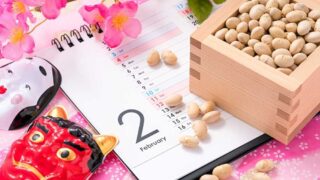こんにちは!
春休みに入ると、夜ふかしや朝寝坊で生活リズムが乱れがちになり、不規則な生活に陥りやすいお子さんが増える時期です。
寝すぎや朝起きられないというお子さんとは反対に、私たち親世代は疲労や更年期の影響で、寝つきが悪い・寝ても疲れが取れないなど、睡眠不足を感じることもあるでしょう。
また、春は寒暖差の影響で体調も崩しやすい季節。だからこそ今が、新生活に向けて「親子で睡眠習慣をリセットするチャンス」なんです。
春の不調に関する記事はこちらから!
しかし、年齢やライフステージによって、睡眠にまつわる悩みの“背景”は異なります。
この記事では、成長期のお子さんと、子育て真っ最中で睡眠に変化が現れやすい更年期を迎えるお母さん方に向けて、それぞれ睡眠の特徴と課題をわかりやすく解説しながら、家族みんなでできる共通のリセット習慣をご紹介します。
今のうちに親子で“睡眠リセット”を意識しておくと、4月からの新生活がスムーズに始められます。
春からの毎日を、もっと心地よく、もっと元気にするために、ぜひ一緒にチェックしてみてくださいね。
なぜ睡眠が大切なのか?親子で知っておきたい基本
質の高い睡眠は、私たちが生きていく上で不可欠です 。
睡眠は、単に体を休めるだけでなく、脳や心臓血管・代謝・内分泌・免疫、認知機能・精神的な健康の維持や増進に重要な役割を果たしています 。
しかし、現代社会では、十分な睡眠をとれている人の割合は決して高くありません。
厚生労働省の調査によると、睡眠によって十分に休養がとれていないと感じる人の割合は年々増加傾向 にあります 。
日本人の睡眠時間は、海外と比べても短い傾向があり、約4割の人が1日に6時間未満しか眠れていないと言われています。加齢とともに睡眠時間は少しずつ減っていき、成人後は20年ごとに30分ほど短くなるとも考えられています。
以下は、各年代の睡眠推奨時間の比較をまとめてみました。
| 年齢層 | 推奨睡眠時間 | 実際の平均睡眠時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 4ヶ月~ 1歳未満児 |
12~16時間 (昼寝含む) |
約13〜14時間 | 比較的しっかり 眠れている傾向 |
| 1~2歳児 | 11~14時間 (昼寝含む) |
約12時間前後 | 就寝時間が やや遅くなる傾向も |
| 3~5歳児 | 10~13時間 | 約10〜11時間 | 園児の生活リズムに 左右されやすい |
| 小学生 | 9~12時間 | 約8〜9時間 | 推奨よりやや 短めになる傾向 |
| 中・高生 | 8~10時間 | 約6.5〜7.5時間 | 部活・塾・スマホで 慢性的な睡眠不足 |
| 成人(20~64歳) | 6~8時間 | 約6.5時間前後 | 女性は6時間未満が 増加傾向 |
| 高齢者(65歳以上) | 7〜8時間(目安) | 約6時間前後 | 中途覚醒が増え、早寝早起き傾向 |
※実際の平均睡眠時間は、厚生労働省「21世紀出生児縦断調査」などの統計情報を参考にしています。睡眠時間には個人差もあります。
親子で睡眠不足が招く影響|成長期~更年期
睡眠には年齢やホルモンバランスによって質の違いがあります。
成長期の子どもは、深いノンレム睡眠中に成長ホルモンが分泌され、心身の発達に欠かせません。
一方、更年期の女性は、エストロゲンの減少により自律神経が乱れ、眠りが浅くなったり、夜中に目が覚めたりしやすくなります。
つまり、親子で同じように寝ているつもりでも、必要な睡眠の質は異なるのです。
小学生|生活リズムの乱れに注意!成長ホルモンと深い関係
小学生は、睡眠中に多く分泌される“成長ホルモン”が心身の発達に欠かせない時期です。
しかし、春休みの生活リズムの乱れや、夜遅くまでゲームやテレビを続け、夜更かしのクセが新年度に持ち越されると、朝起きられずに学校がつらくなる原因にもなります。
デジタル機器から発せられるブルーライトは、睡眠を促すホルモンであるメラトニンの分泌を抑制し入眠を妨げやすくなります。
睡眠不足は集中力や記憶力の低下を招き、学業成績にも悪影響を及ぼす可能性があるのです 。
中高生:思春期特有の“夜型化”と睡眠負債の蓄積
思春期になると、体内時計のリズムが後ろにずれる「睡眠相後退」が起きやすくなり、自然と“夜型”になりがちです。
そこに部活動や塾、スマホの使用などが加わると、就寝時刻はさらに遅くなり、平日の睡眠時間が足りなくなる「睡眠負債」に。
週末に寝だめをしても、体内時計の乱れを助長し、かえって月曜がつらくなるという悪循環を招きます。
成長ホルモンは、深い睡眠中に活発に分泌される ため、「眠りのゴールデンタイム」を確保することが大切ですね。
更年期世代:ホルモン変化による睡眠の質の低下
更年期を迎える親世代では、ホルモンバランスの変化により、睡眠が浅くなったり、夜中に目が覚めたりすることが増えます。
女性の場合、エストロゲンやプロゲステロンの減少により自律神経が乱れ、ホットフラッシュや発汗などが夜間の睡眠を妨げることも。
男性も加齢とともに睡眠の質は低下傾向にあり、生活習慣病やストレスが眠りに影響を与えているケースも少なくありません。
睡眠が不足すると、日中の眠気や疲労感だけでなく 、頭痛をはじめとする心身の不調が増加し、感情が不安定になることもあります。
さらに、注意力や判断力が低下し、仕事や勉強の効率が悪くなったり、思わぬ事故につながる可能性も指摘されています 。
慢性的な睡眠不足は、生活習慣病の発症リスクを高めたり、病状を悪化させることもあります ..。
そして、睡眠不足は、痩せにくい身体を作ってしまうダイエットの大敵なのです。
「年齢のせい」とあきらめず、できることから生活を見直すことが大切です。
親子で取り組める!共通の睡眠リセット習慣
それぞれの世代に異なる課題があるとはいえ、良い眠りをつくるための“基本”は共通しています。
以下のポイントは、年齢にかかわらず家族みんなで実践できる、睡眠のリセット術です。
- 朝は太陽の光を浴びて、体内時計をリセット
- 毎日同じ時間に起きて、朝食をしっかり摂る
- 日中は体をよく動かし、夜はリラックスする時間を作る
- 就寝前1時間はスマホやテレビなどの使用を控える
- 寝室の環境(温度・湿度・光・音)を整える
- 夕方以降のカフェイン摂取は控える(お茶・コーヒー・チョコなども)
これらの小さな習慣が、睡眠の質をじわじわと底上げしてくれます。
快眠のカギは「食生活」にもある!
睡眠を整えるためには、生活リズムだけでなく「食事の内容」も重要な役割を果たします。
特に、トリプトファンやビタミンB6、マグネシウム、鉄分といった栄養素は、神経の安定やホルモン分泌、体温調節などに関与しており、快眠には欠かせません。
ただし、どの食材に含まれているのか、どうやって取り入れればいいのか迷う方も多いのではないでしょうか?
そこで、次回は睡眠と食事との関係をテーマに「眠りをサポートする栄養素と食事の工夫」について詳しくご紹介します。
➡『ぐっすり眠るための栄養素と食べ方のコツ』の記事も近日公開予定です♪
この春、新しいスタートとともに、親子で“眠り”を見直してみませんか? 暮らしのリズムが整えば、きっと毎日がもっと軽やかになりますよ。
まとめ:眠ることは、元気を取り戻す力
睡眠は、親子の健康や心の安定を支える“土台”です。春は、そんな土台を見直す絶好のチャンス。
成長期の子どもには、成長ホルモンをしっかり分泌させる深い眠りが必要です。
そして、更年期を迎えるお母さん方には、自律神経を整え、代謝を保つための質のよい睡眠が欠かせません。
親子で一緒に睡眠を見直すことで、体調も気持ちもぐんと軽くなります。
新年度は、お子様の進学や進級、ご自身の生活環境の変化など、何かと慌ただしい時期です。まずは、できることからでOK。
この機会に、春のスタートに「快眠リセット」始めてみませんか?
こちらもチェック
- Blossomの大切にしている想いについて、詳しくはこちらをご覧ください
- Blossomのコンセプト Blossomの具体的な取り組みはこちらから
- ワークス
最後までお読みいただき、ありがとうございました。