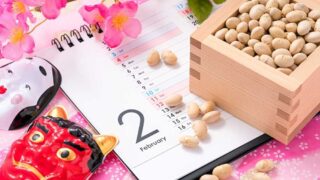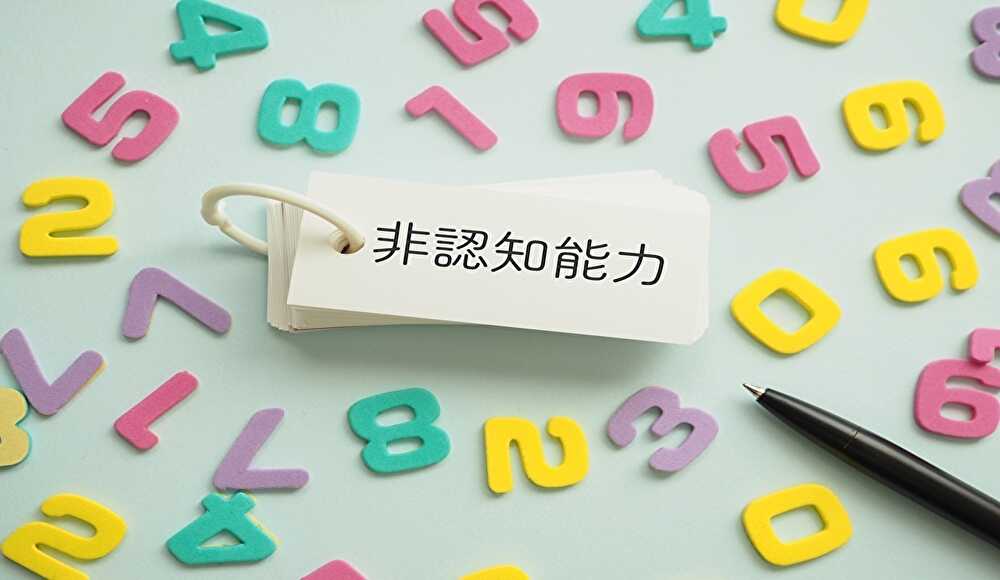こんにちは。
先日、次男の中学校保護者会に参加した際、学年主任の先生が「非認知能力を育てることの大切さ」に触れお話されていました。
学力や成績だけでなく、社会の中で自分らしく生きていくための“見えない力”を育てたいと話されていたのが印象的でした。
公立中学でどこまで踏み込めるのかという現実的な問題もあるかもしれませんが、こうした話題が出るようになったことに希望のようなものを感じました。
私自身も、非認知能力の重要性を深く実感しています。
特に、長男が大学進学で家を出て一人暮らしを始めてから、その思いはより強くなりました。
テストでは測れない力とは?いま注目される“非認知能力”
非認知能力とは、テストの点数では測れない力のことを指します。
たとえば以下のような力が挙げられます。
- やり抜く力(グリット)
- 自己肯定感・自信
- コミュニケーション力・共感性
- 自律性・計画性
- 感情のコントロール
これらは学力とは異なり、数値化しづらいものですが、将来の人生において欠かせない土台となる力とされてます。
社会に出てから、人間関係を築いたり、自分らしく生きていくために必要な“生きる力”とも言えるでしょう。
どこで育つのか?家庭や日常がカギを握る理由
では、この非認知能力はどこで育まれるのでしょうか?
実は、特別な場や教材が必要なわけではありません。
日々の生活、家庭での関わり、失敗と成功の体験の中に、そのヒントがあるのではないでしょうか。
- お手伝いや家事を通じて責任感を学ぶ
- 自分で考え、行動する経験から自律心が育つ
- 家族との会話や衝突を通して、他者を思いやる力が磨かれる
- 小さな成功体験の積み重ねが、自信や達成感につながる
こうした日常の中の出来事が、非認知能力の“育ち場”だということですね。
成長の実感|一人暮らしを始めた息子の変化
大学進学を機に一人暮らしをしている長男ですが、離れてみて彼の中に育っていた「非認知能力」の存在にふと気づくことが増えました。
もちろん家賃や生活費などの仕送りもしっかりしていますが、自炊をしながらアルバイトもこなし、サークルや仲間との交流も楽しみつつ、本業である勉強にもきちんと取り組み、自己管理ができている様子。
先日はゴールデンウィークに帰省し、「親のありがたみがわかった」とぽつり・・。
なんと、バイト代で私に日傘をプレゼントしてくれました。その日傘をさすたびに、彼のやさしさと成長を思い出します。
また、庭の手入れを手伝ってくれたり、運転を買って出てくれたりと、「自分ができることをする」という姿勢にも、頼もしさを感じました。
こうした“ちょっとした行動”のひとつひとつが、まさに非認知能力の現れだと感じています。
私たちができること|家庭で育む“非認知能力”のヒント
非認知能力は、親の関わり方次第で大きく育ちますが、特別なことをする必要はありません。
以下のようなことを、日常に少し意識して取り入れてみるとよいかもしれません。
- お子さんに「任せる場面」をつくる(小さな家事や買い物など)
- 結果より「過程」を認める声かけをする(「頑張ってたね」「工夫してたね」など)
- 私たち自身も完璧を目指さず、失敗も共有する
- 食卓や送り迎えなど、何気ない時間を会話の場にする
そして何よりも、お子さんを信じて見守る姿勢が大切なのだと思います。
目に見えないけれど、確かに育っていく力。それを信じて寄り添うことが、非認知能力を育む一歩になるのではないでしょうか。
まとめ|人生を切り拓くために
学力や偏差値ももちろん大切ですが、社会で長く生きていく上で必要なのは、点数では測れない「人としての力」ではないでしょうか。
息子の姿を見て、私自身もあらためて実感しています。
子どもが自分の人生を切り拓いていけるように、私たち親にできること。
それは、家庭という“安心できる場”で、見えない力の芽を信じて育てていくことかもしれません。
最後までお読み頂き、ありがとうございました✨
こちらもチェック
- Blossomの大切にしている想いについて、詳しくはこちらをご覧ください
- Blossomのコンセプト Blossomの具体的な取り組みはこちらから
- ワークス